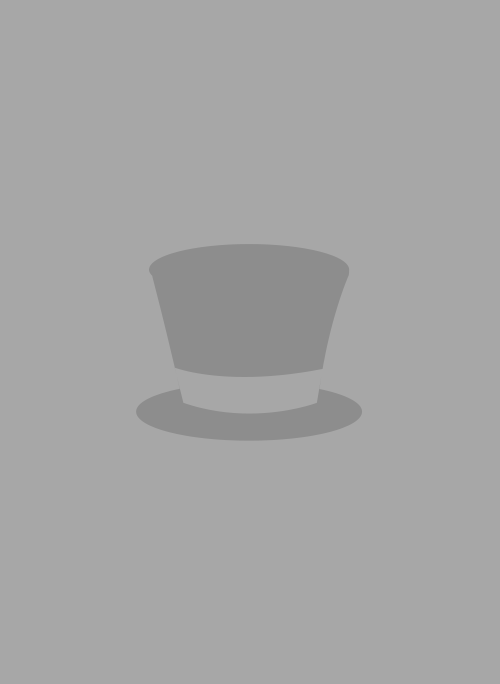「好きなんだ、なっちゃんが」
「雅…」
彼は優しく微笑んだかと思うと、急に強張った表情で信太郎の言葉を遮り、大声をあげた。
「好きなんだよ!ずっと前から!だからああした!」
そんな彼の様子に、信太郎は何も言えなくなってしまった。
波が砂を洗っていく音がひっきりなしに聞こえてくる。
しばらくして「なぁ、雅樹」と、信太郎はできるだけ穏やかに親友の名を呼び、言った。
「おまえがナツを好きなことはわかった。いや、ずっと前から知ってたよ。でも、今じゃなくてもいいだろ。あいつはただでさえばぁさんが死んで不安定なんだ。そんなことしたらもっと…」
「だからだよ、だから俺がそばにいるってことをわかってほしかった。なっちゃんをいつだって支えてやれるやつがいるから、安心しろって」
雅樹が苦しげに顔を歪め、うつむいた。
「ああすることでナツが安心すると思うか?かえって混乱するんじゃないか?」
「信太郎」
普段の柔らかな声色とは違う、芯の通った雅樹の声が信太郎をとらえた。
「おまえが怒ってるのは、俺がなっちゃんにしたことが彼女の気持ちを不安定にさせるからか?」
「……」
「違うだろ、もっと単純なことで怒ってるんじゃないのか?」
「どういう意味だよ」
「俺がなっちゃんにキスをした、ただ単にそれが気に入らないんだろ」
信太郎の右の頬がピクリとひきつった。
「おまえだって、なっちゃんのこと…なのに違う子と付き合って自分の気持ちをごまかしてる」
「あーあ、くっだらね」
小鼻をポリポリかくと、信太郎は吐き捨てるようにそう言った。
「信太郎」
「あ、そうだ、雅樹さぁ、ツバサから連絡あって、夏休み中に泳ぎにいこうってさ」
「話そらすなよ」
「いつがいい?来週辺りはどう?早くしないとクラゲが出てくるしさ」
「信太郎!」
雅樹は苛立ったように足元の砂を蹴った。