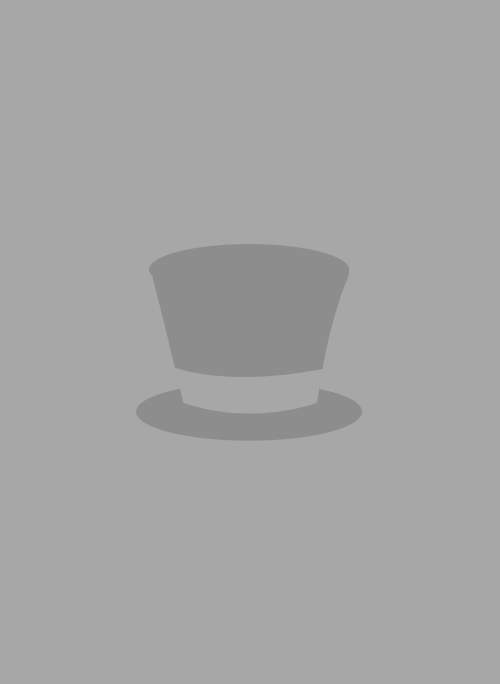どうしてあの時断らなかったのだろう。
こんなにも信太郎が好きなのに、どうしてだろう。
どれだけ傷つく言葉を投げかけられても、この心はいつも彼を想っている。
それなのにどうしてだろう。
夏海は卓上カレンダーに目をやった。
今日は3月20日。
2週間近くも彼と連絡を取っていない。
K大の後期試験も終わったはずで、その合格発表がいつなのかもわからない。
もうどうでもいい、そんな気持ちが微かにあるのは確かだ。
このまま終わってしまうのだろうか、自分たちは…
パソコン画面がみるみるうちに滲む。
「おーい、佐々倉さん。どした?」
課長がとうとう席を立って夏海に近付いてきた。
「すみません!花粉症がひどくて!」
ティッシュを何枚か引き抜くと、彼女はわざと大きな音をたてて鼻をかんだ。
腰掛けた防波堤から足を投げ出し、夜の打ち寄せる波の音を聞く。
「…信ちゃん」
これで何度目だろう。
何度彼の名を呼べば、気がすむのだろう。
結局は他人事なんだよな、彼は確かにそう言った。
自分は信太郎を想っていた、想っていたからこそ、彼の夢に続くこの一年間を邪魔したくなかった。
会いたくても、ぐっと我慢した。
それが夏海なりの「想い」だったのに、彼はそうは感じなかったのだろう。
じゃあどうすればよかったのか。
もう何もかもが夢だったらいいのに。