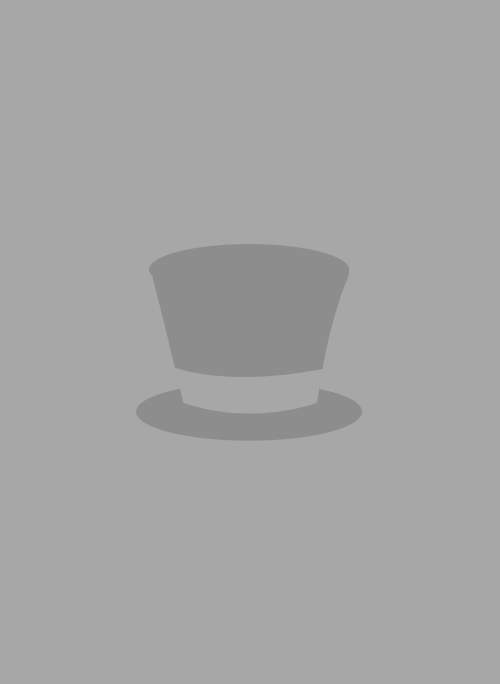「佐々倉さん、手が止まってるよ」
課長が渋い顔で離れたデスクから声をかけた。
「あ…」
すみません、それすらも声にならなかった。
夏海は頭を下げると、パソコンのキーボードに置いたままの指を動かす。
昨晩の父の言葉が耳から離れなかった。
キッチンで夕食の支度をする彼女に、改まった様子で克彦が言った。
「正式に町長から見合いの話があったんだ。どうする?」
「どうするって…」
包丁を握る手が止まる。
「お見合いって言うと仰々しいな。まぁとりあえず息子さんと会ってほしいって」
「いくつだっけ、その人」
「今年30」
一回り近く上である。
「断っていいんだろ?」
克彦は夏海の気持ちを確認するように訊ねた。
「その返事、いつまでにすればいいの?」
「え?だっておまえ…」
「いつまでかって訊いてるじゃん!」
振り返った娘の険しい表情に、克彦はビールを飲む手を止めた。
信太郎と何かあったのか、そう訊きたくてもできない雰囲気を彼は察し、一息ついた。
「できたら今月中に、ということだよ」
「…考えとく」
「なぁ、夏海…」
「いけない、洗濯物取り込むの忘れてた。もう冷たくなっちゃったかも」
父の声などまるで聞こえていないかのように、夏海は手を拭きダイニングを出た。
信太郎の話が出るに決まってる、そう思ったのだ。
彼以外に考えられない、そう言い切ったのに…。
彼女は乱暴に洗濯物を取り込むと、バスケットの中に押し込んだ。