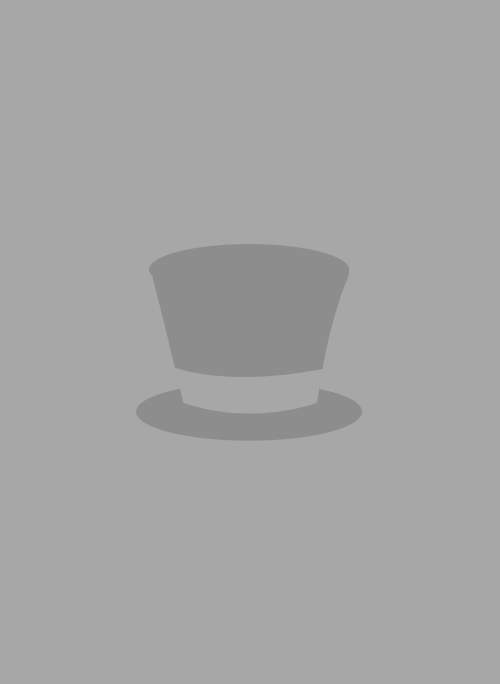「信ちゃんは大丈夫。頑張ってるんだから。きっと神さまも見てるよ、ね?」
「は?神さま?」
目をつりあげて振り返った彼に、夏海は一瞬で凍り付いた。
「何の神さまだよ、言ってみろよ」
「…信ちゃん」
「しかもなんでおまえが泣いてるんだよ。俺がかわいそうだからか?それとも今回も落ちたよ、これじゃ、また会えないじゃんって、遊べないじゃんってそんなこと思って、どうせ泣いてるんだろ!」
夏海の唇が小刻みに震えた。
そんな彼女に信太郎は小さく舌打ちすると、天を仰いだ。
沈む太陽を追いかけるように、細い三日月が西の空に浮かんでいる。
「信ちゃんはさ、そんなふうに私のことを思ってたんだね」
「……」
「そっか、そうだったんだ。参ったな…」
えへへ、と頭をかくと、夏海は自転車を押した。
あの夜みたいに、好きだと言ってくれた時みたいに、今また腕をつかんで抱きしめてくれたら…
しかし、信太郎は空を仰いだまま目を閉じ、微動だにしない。
夏海はたまらず走り出した。
カラカラカラ…と今度は早く、そして切ないペダルの空回りする音が辺りに響き、やがて信太郎から遠ざかっていった。