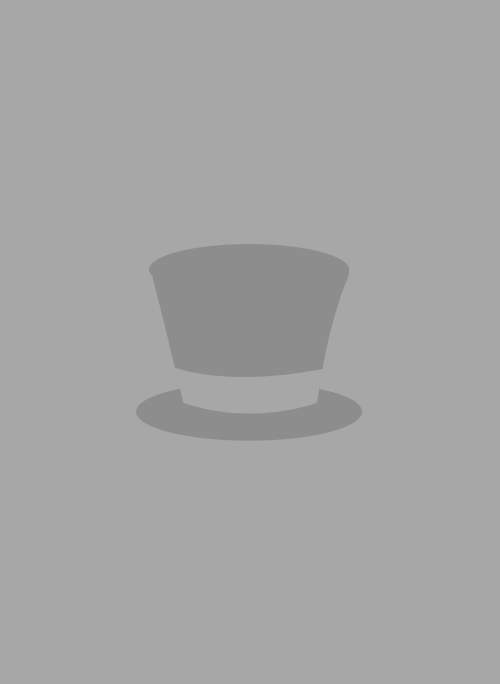カラカラカラ…とペダルの空回りする音が、静かな豊浜の坂にこだまする。
夏海は自転車を押しながら、信太郎とふたりで歩いていた。
「後期試験って、やっぱりK大?」
「ああ」
「私大は受けなかったの?滑り止めってやつ…」
「受けてない」
少しうっとうしそうな声色で、彼は短く答えた。
「どうして?」
「俺にとってK大じゃなきゃ意味がないんだって。散々おまえにも話したよな?そこが宇宙工学の分野では日本一なんだって」
そうだけど…と言いかけて夏海は思い止まり、代わりに「そうだったね」と答える。
苛立った彼の口調にこれ以上何も言うべきではないと思ったからだ。
しかし、次に彼の口から出てきた言葉に、夏海の足が止まった。
「ったくおまえはいいよな、お気楽で。頑張ってって言っても、結局勉強するのは俺、試験受けるのは俺、不合格で悔しがるのは俺。ナツにしてみたら、他人事なんだよな」
そんなふうに思ってたの?
あまりのことに声が出なかった。
ガン、と頭を打ちのめされたような衝撃的な彼の言葉。
夏海にかまわず歩き続ける信太郎は、たたみかけるように言った。
「あーあ、俺も進学せずにじいさん、ばあさんに親切にしてたら、うちの孫の婿に来てくれないかって言われて、逆玉のれるかもなぁ」
明らかに夏海を皮肉ったものだった。
どうしたのだろう、彼は。
そうか、きっと辛いんだ、だからこんなことを言うんだ。
今の彼をありのまま受け入れることができるのは、自分しかいないのだ。
知らぬ間に頬を伝った涙を拭うと、彼女は努めて明るく言った。