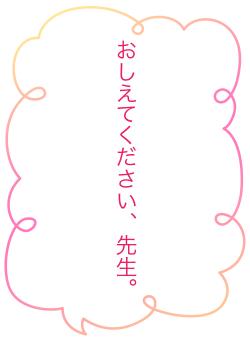俺を庇うように飛び込んだ親父の背中にブスリと、ナイフが刺さっていた。
真っ赤に染まる視界、鉄のような嫌な匂い。
「お……じ……?」
久しぶりに出した声は掠れていて、うまく音にならなかった。
「隼……ごめん……」
「……な……が…………」
「気づいてあげられなくて……ごめんな……」
ぎゅっと、親父が抱きしめてくれる。
何年ぶりの、温もりだろう。ずっと、これが欲しかったんだ。誰かに、抱きしめてもらいたかった。
「アハ……アハハハハハハハハ!!!!」
女の笑い声が響く部屋で、俺は幸せを感じていた。
「隼、愛してる……」
「お……」
俺もだよ、親父……。
言いたい言葉は、声にならない。
親父の胸に、顔を埋める。
あぁ、まだこうしていたい。親父と一緒にいたい。死にたくない。死んでほしくない。親父と一緒に、生きていきたい。
――ブォンブォンブォン
バイクの音がする。
この音は……蓮のバイクだ。
ああ、蓮が来てくれたんだ。蓮なら、なんとかしてくれる。
そう思うと、安心して体の力が抜けた。そっと目を閉じる。
次に気がついた時、俺は病院のベッドの上だった。