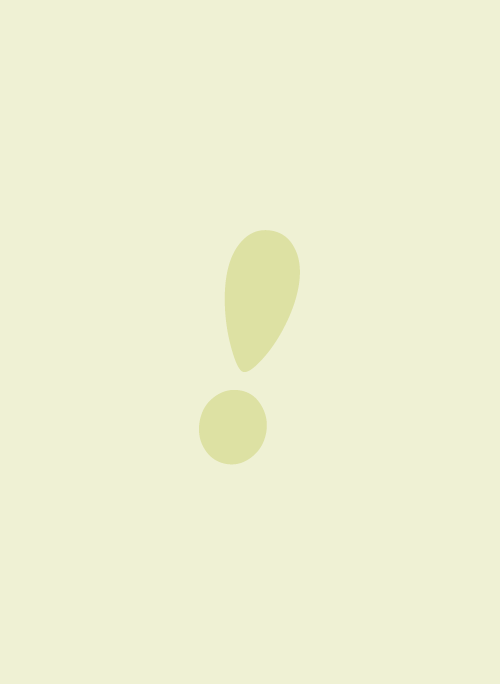「所で女の子の心に光りを照らすにはどうしたらいいの?」
(うむ、別に本人にじゃなくてもよい。まぁ、例えばその子が身につけているものに光り魔法を注げばよい。)
カナルは、悩んだ。実際に女の子とは友達ではないし、名前さえ知らなかったので近づきようがなかったのだ。
次の日。
カナルは、学校で女の子を探していた。ちなみにカナルは一年一組、女の子は二組だ。
カナルは、教室を除きこんだが、女の子はいなかった。
「どいて、入れないよ。」後ろから声が聞こえてカナルは、慌ててどいた。
「あっ、ごめん。あっ!」
あの女の子だった。カナルは、女の子と目が合い固まってしまった。そんなことをしているうちに女の子は教室に入ってしまった。
「見たぞ、見たぞ!」健ちゃんがニヤニヤと、にやけながらカナルに近づいてきた。
「もうだから違うんだって!」カナルは、一生懸命否定したが、健ちゃんの耳には聞こえていなかった。
「よしっ!カナル。僕が協力してあげるよ!」と言うとカナルが止める暇もなく健ちゃんは二組の教室に入っていった。カナルは、どっと疲れたので教室に戻り、自分の椅子に座るなり、図書室で借りた本を開いて、健ちゃんの帰りを待った。
そして、健ちゃんは風のように素早く一組の教室に戻ってきた。
「カナル!聞いて。」
「健ちゃん、早かったね。あの子に変なこと言ってないだろうな?」
カナルは、少し膨れていた。
「そんなことしないよ!だって僕もあの子のこと知らないし。」
「じゃあ、何しにいったの?」カナルは、きょとんとした。
「実は、二組に僕の家と隣りの女子がいて、そいつにあの子のことを聞いてきたんだよ。」
カナルは、考えた。
「健ちゃん、聞くのはいいけど、その家が隣りの子にはなんて説明したの?」
「…。」健ちゃんは、カナルと目を合わさずに動揺して喋らなかった。
「…あっ!やっぱりいらないこと言ったなー!」
健ちゃんは、逃げた。「ごめ〜ん!許してー!」、「許さなーい!」カナルは、追いかけた。
授業の鐘がなり、慌てて二人は教室に戻ったが、カナルは口パクで謝ってくる健ちゃんを無視した。
(うむ、別に本人にじゃなくてもよい。まぁ、例えばその子が身につけているものに光り魔法を注げばよい。)
カナルは、悩んだ。実際に女の子とは友達ではないし、名前さえ知らなかったので近づきようがなかったのだ。
次の日。
カナルは、学校で女の子を探していた。ちなみにカナルは一年一組、女の子は二組だ。
カナルは、教室を除きこんだが、女の子はいなかった。
「どいて、入れないよ。」後ろから声が聞こえてカナルは、慌ててどいた。
「あっ、ごめん。あっ!」
あの女の子だった。カナルは、女の子と目が合い固まってしまった。そんなことをしているうちに女の子は教室に入ってしまった。
「見たぞ、見たぞ!」健ちゃんがニヤニヤと、にやけながらカナルに近づいてきた。
「もうだから違うんだって!」カナルは、一生懸命否定したが、健ちゃんの耳には聞こえていなかった。
「よしっ!カナル。僕が協力してあげるよ!」と言うとカナルが止める暇もなく健ちゃんは二組の教室に入っていった。カナルは、どっと疲れたので教室に戻り、自分の椅子に座るなり、図書室で借りた本を開いて、健ちゃんの帰りを待った。
そして、健ちゃんは風のように素早く一組の教室に戻ってきた。
「カナル!聞いて。」
「健ちゃん、早かったね。あの子に変なこと言ってないだろうな?」
カナルは、少し膨れていた。
「そんなことしないよ!だって僕もあの子のこと知らないし。」
「じゃあ、何しにいったの?」カナルは、きょとんとした。
「実は、二組に僕の家と隣りの女子がいて、そいつにあの子のことを聞いてきたんだよ。」
カナルは、考えた。
「健ちゃん、聞くのはいいけど、その家が隣りの子にはなんて説明したの?」
「…。」健ちゃんは、カナルと目を合わさずに動揺して喋らなかった。
「…あっ!やっぱりいらないこと言ったなー!」
健ちゃんは、逃げた。「ごめ〜ん!許してー!」、「許さなーい!」カナルは、追いかけた。
授業の鐘がなり、慌てて二人は教室に戻ったが、カナルは口パクで謝ってくる健ちゃんを無視した。