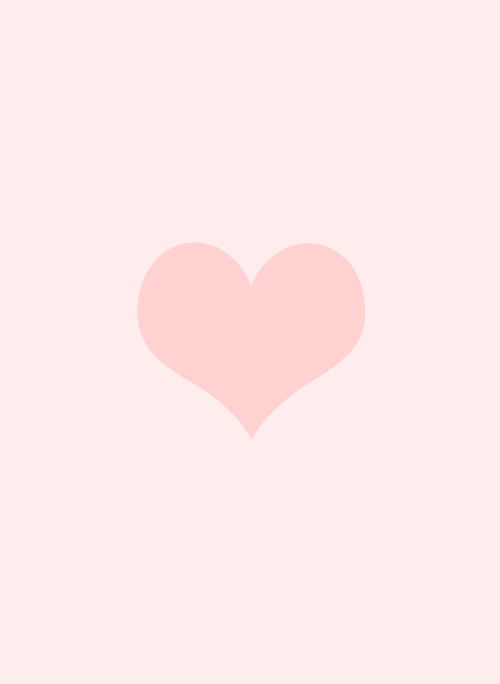「――――もうこれ以上、誰も失いたくないよぉ…」
再び甦る源九郎の死が政宗と重なり、寒気がした。
震え上がった肩を自分自身で抱く。
涙を拭ってもらったあのとき、ひすいは政宗を信じることにした。
視界が開けた瞬間、目の前に現れた澄んだ隻眼には奥から光が溢れてくるようで、ひすいはその眼から背くことを忘れた。
その隻眼にまた、包まれたいと何や何やらわからぬ感情が渦巻いていた。
「……母様!」
と、聞こえるはずのない梵天丸の声が地面から微かに聞こえた。
ひすいは反応し、辺りを見回してみたが梵天丸どころか人さえもいない。
あまりの当惑に気がやられたのだろうと、また顔を俯かせようとするとまた、
「母様…!」
今度は確かに聞こえた。
「梵天丸?どこ…?」
ひすいが這いつくばって声のもとへ近づいていくと、どうしたものか、先程までなかった壁の根元に人ひとりがやっと入れるような穴が開いていた。
「母様、こちらでごさいます…!」
決して大きくはないその声があの穴から聞こえるのだと思うと、ひすいはすぐに駆け寄って覗き込んだ。
見れば、そこには暗い空間の中に手を大きく広げる梵天丸と、辺りを注意深く警戒している小十郎の姿があった。