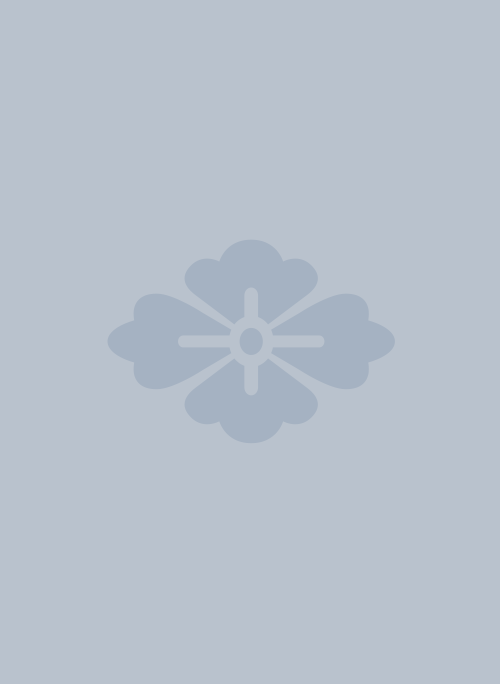あてた手から彼の心の臓の鼓動が伝わってくる。
当たり前のことだが、それが生きているという感覚を蘇らせる。
自分も、目の前の彼も生きている。
この世に命を落としたときから人は与えられた運命がある。
時には伴侶を見つけ、共に支え生きていく者もいる。
しかし、この人は自分とは異なるのだ。
ひすいは嘲るように鼻で笑った。
「あんた、俺がどんな人間かわかってんのか?俺は大名でも、豪族でも、ましてや城下の者でもねぇ。何にも属さない、長い間虐げられてきた山賊の頭だ。こんな穢(けが)れた俺を愛して、一体あんたに何の利があるっていうんだよ」
「利はいらぬ、ただお前の愛が欲しい」
「あんたは大名だ。それ相応のお姫様と祝言でも挙げてろ」
ひすいは手で政宗を押し返そうとしたが、全く効果がない。
「………お前は小十郎が好きなのか?」
ふと、ひすいの頭の後ろから声が聞こえた。
「お前は小十郎に惚れておるから、俺の愛を受け入れられないと申すのか」
他人に改めて言われて当惑する。
自分は果たして小十郎に惚れているのか?
あの例えようのない高揚は、彼への想いが故の賜物なのだろうか?