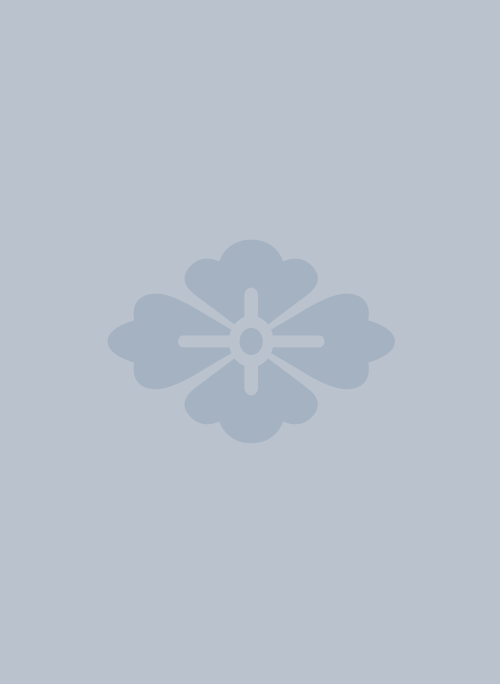「見たいのか、見たくないのか」
持ち越されている返答に痺れを切らし、政宗はひすいに詰め寄った。
その差は一寸にも満たない。
「ち、近ぇよ」
「お前の答えを聞くまで離れぬ。何ならこのまま口吸いもできるがな」
「――――――――…観てやるよ」
ため息と伴に漏らした言葉はほとんど諦めたような気持ちが混じっていたが、政宗は全く気にせず、満足そうに頷いて梵天丸の手を引き、ある程度の広さがある庭へ赴いた。
―――――父子は相対する。
二間(約3メートル)ほど離れ、両者ともそれぞれの丈に適した木刀を差し向けていた。
政宗は瞳を閉じて全身で風を感じ、そこから梵天丸の『気』も感じ取っていた。
ゆっくりと開眼する彼の目は先程のものとは似て非なるものである。
まさに、集中は全て梵天丸へと注がれているのだ。
「…………来い」
父がそう呟くと梵天丸は奥歯を噛みしめて、次には地を蹴っていた。
重なる木刀のくぐもった音が幾度と繰り返される。