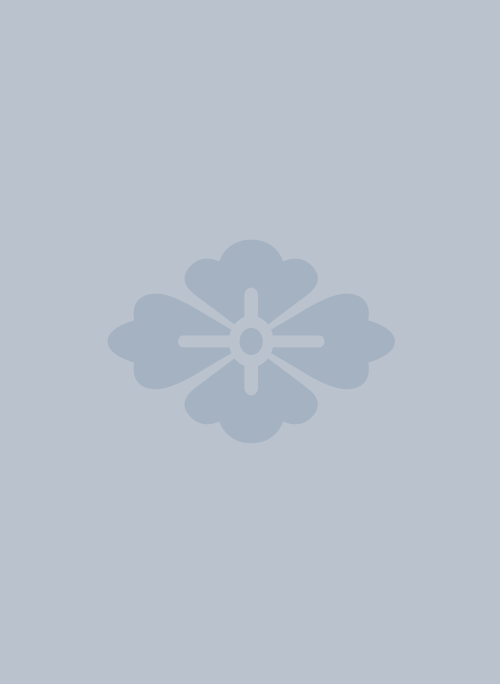「父様は瓜が幼い頃からお嫌いらしく、小十郎がいなくなった隙をついては父様は人参を、僕は瓜を食べていることもよくあるのですよ」
梵天丸は無邪気に笑った。
小十郎に見つかるか否かの瀬戸際で、父である政宗と共にで何かをするのが余程楽しいのだろう。
そんな情景が何の障りなく浮かんできて、ひすいは頬を緩ませながら半分、羨望した。
「愉しそうだな」
つい口が呟いてしまったと気付くときには既に遅く、その声は梵天丸の耳にしかと入っていた。
目を瞬かせ、彼女にその意味を問うている。
生憎、梵天丸には僻みには聞こえなかったらしい。
それだけで、ひすいは胸を撫で下ろした。
すると、中庭の先から土を踏む音が聞こえてきた。
「なんだ、ひすいではないか」
現れたのは梵天丸と同じ格好である袴姿の政宗だった。
「政宗さん……」
「なんだ、俺の稽古を見に来たのか?」
相変わらず、調子の良いことを言うものだ。
不適に笑う政宗はやはり男であるが美しい。
口角を吊り上げ、ひすいを見つめるのは想い人を眺める姿そのものである。
それを知っているかは定かではないが、ひすいは何故か負けじと政宗を見つめ、――――否、睨み返していた。