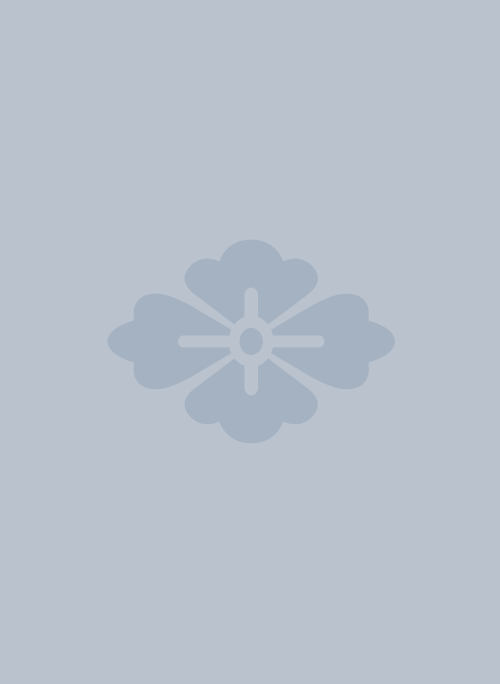「貴方様の母君になれるよう、心尽くしたいと思いますわ」
まるで他人のような言葉遣い。
本当に母なのか?
疑問を抱くが、それでもあの小十郎が嘘をつくとも考えられない。
ならばどうして?
その心の疑問に答えるかのようにまた、小十郎が言う。
「彼女は『ひすい』さんであることを棄てました。これから、政宗様、そして梵天丸様のお側に居なさるための唯一の方法であるのです…」
「――――…ならば、僕はあの方を義理の母と呼ぶしかないのですか?」
「…………」
それには答えてくれなかった。
彼なりにも考えがあるのかもしれないが、その表情は言いたいが言えないような悔しさが入り混じったものであった。
しかし、これからは母がいるのだと思うとそうはいってもやはり嬉しいものがある。
もう一度、その姿を見たいと何度想い馳せただろうか。
「華様を『母様』と………そう呼ばせて下さい」
かつての母であるなら今はそれでいいではないか。
梵天丸は華に笑いかけた。
また彼女もそれに応えるように一層微笑みを深くする。
「はい。喜んで」
優しく紡がれた言葉に癒されるとともに、美しく笑う女人であるのだな、と関心する梵天丸であった。