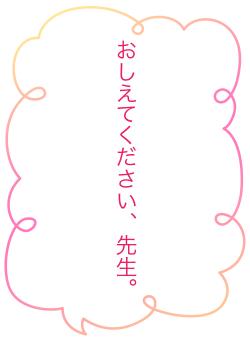視界に、弾け飛んだボタンが映る。
その光景に重なるように浮かぶのは、現実じゃないとわかっている。
脳裏に刻まれた、あの日のことだとわかっている。
――だけど。
あたしが思い出すのは、あの日のこと。
怖くて、怖くて、ただただ怖くて気持ち悪くて痛かった、あの日のこと。
「…や、嫌ァ!!!!」
最早あたしに見えているのは“星宮千早”じゃ、ない。
「いや、やめてっ!!」
あの時の、幼かった自分と同じように声を上げる。
手が伸びて来て、でもその手はあたしを助けてくれる手じゃなくて。
あたしを地獄に突き落とした、手。
必死に抵抗したって、男の力には敵わない。
そんなこと、幼かったあたしだって知っていた。
だけど、やめられなかった。
怖かったから。
殴られても、触られても、吐きそうになっても、怖かったから。
「そうそう、嫌がってくれないと面白くないからね」
声は星宮千早なのに、あたしの目にはあの日のニヤニヤと気持ちの悪い笑みを浮かべた男が見えた。