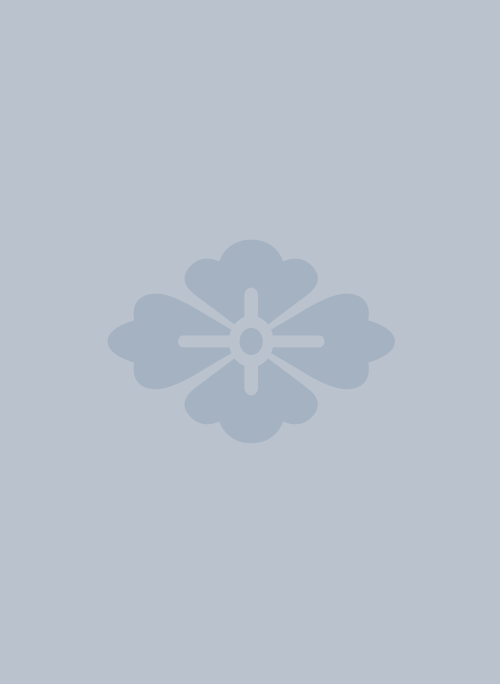……それから、約三十分後。
シェリーの電話を受けて、慌てて帰って来たハニーを抱きしめて。
僕は、ようやく。
意志で歯止めをかけていた欲望を全部、解放することが出来た。
ハニーが着ている通勤用のスーツを全部脱がしてしまうのも、もどかしく。
からからに渇いた喉を癒すかのように。
ハニーのしなやかなカラダをむさぼり、抱いて、抱いて。
ようやく、満足した頃。
へとへとになった僕を、浴室の湯船に放り込んで、今度は。
ハニーの方が、僕を抱きしめた。
「……例え、インフルエンザにかかって、高熱を出しても。
私の職場(ところ)に、連絡一つよこさない螢が大変だって聞いて、かなり、驚いた」
部屋でのお返し、とばかりに。
浴室で、散々僕を愛してくれたあと。
シェリーからの緊急電話が、こんな用だったのか、と微笑むハニーに、僕は、クビを引っ込めた。
「……ごめん……
もしかしなくても、まだ仕事中だったろ?
変なことに呼び出して、邪魔して悪かったよ」
「……そうでもない。
もう、フレックスの使える時間だったし。
……何よりも、螢が。
私の事を待てないほど、欲しがってくれたのだから、いいよ」
僕のまとった泡々の服を。
暖かいシャワーで、消し去りながら。
ささやくハニーが、とても嬉しそうだった。
だから、ハニーを勝手に呼びつけたのは、実は、シェリーだ。
なんて言えずに、僕は、そっとため息をついた。
そんな僕に、ハニーが心配そうに眉をひそめる。
「……それで。
本当の所、何があったのか。
私は、君に、聞いても良いのかな?」
「ハニー」
「君は、いつも。
自分からは、ほとんど誘ってこない。
しかも、私に抱かれても、自分で抱くことはあまり無いのに。
今日は、やけに情熱的すぎる。
しかも、私は。
螢のここに、跡をつけた覚えが、無いのだが――」