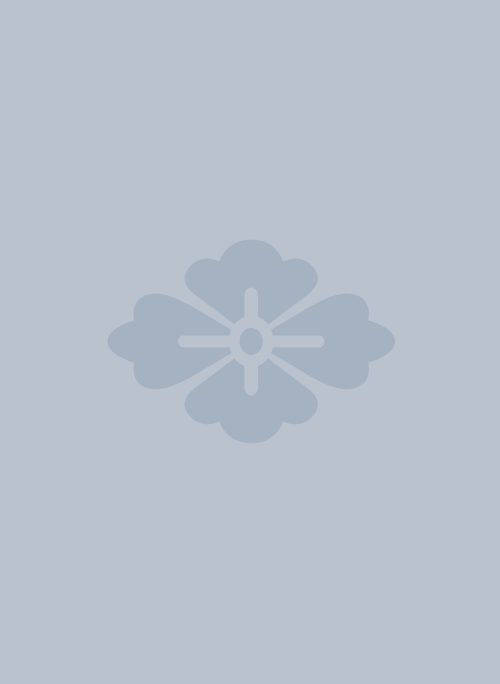「確かに、侮っていたからこそ、暗殺要員に女一人しか送り込まなかったのだろうがな」
昨夜の惨状を思い出し、ルッカサ女王はさりげなくハンカチで口を押さえた。
近くに座る、ラスの横顔を盗み見る。
この綺麗な顔の青年の、どこにあのような残虐性が見えるというのか。
身体つきだって、引き締まってはいるが、鍛え上げられているわけではない。
華奢にさえ見える。
「女王はお疲れか?」
我に返れば、ラスがこちらを見ていた。
「朝からぶっ通しですからな。昨夜も倒れられたのだし、ご無理はよくありませぬ。ただでさえお世話になっているのに、この上我が国のことでお手を煩わすのは心苦しい故、どうぞ気兼ねなくお休みになってください」
「い、いえ、そのようなことは・・・・・・」
言いかけた女王だったが、ラスの濃紺の瞳に射抜かれ、言葉を呑み込んでしまう。
何故か、背筋を冷たい汗が伝うのを感じた。
ラスは口元だけで笑うと、ぱんぱんと大きく手を打った。
すぐに扉が開き、控えていた兵士が姿を現す。
「ルッカサ女王がお疲れだ。失礼のないよう、侍女殿をお呼びしてくれ」
ラスの声に、兵士の後ろから侍女が入ってくる。
何となく、有無を言わさぬ迫力を感じ、女王は一礼して部屋を出て行った。
昨夜の惨状を思い出し、ルッカサ女王はさりげなくハンカチで口を押さえた。
近くに座る、ラスの横顔を盗み見る。
この綺麗な顔の青年の、どこにあのような残虐性が見えるというのか。
身体つきだって、引き締まってはいるが、鍛え上げられているわけではない。
華奢にさえ見える。
「女王はお疲れか?」
我に返れば、ラスがこちらを見ていた。
「朝からぶっ通しですからな。昨夜も倒れられたのだし、ご無理はよくありませぬ。ただでさえお世話になっているのに、この上我が国のことでお手を煩わすのは心苦しい故、どうぞ気兼ねなくお休みになってください」
「い、いえ、そのようなことは・・・・・・」
言いかけた女王だったが、ラスの濃紺の瞳に射抜かれ、言葉を呑み込んでしまう。
何故か、背筋を冷たい汗が伝うのを感じた。
ラスは口元だけで笑うと、ぱんぱんと大きく手を打った。
すぐに扉が開き、控えていた兵士が姿を現す。
「ルッカサ女王がお疲れだ。失礼のないよう、侍女殿をお呼びしてくれ」
ラスの声に、兵士の後ろから侍女が入ってくる。
何となく、有無を言わさぬ迫力を感じ、女王は一礼して部屋を出て行った。