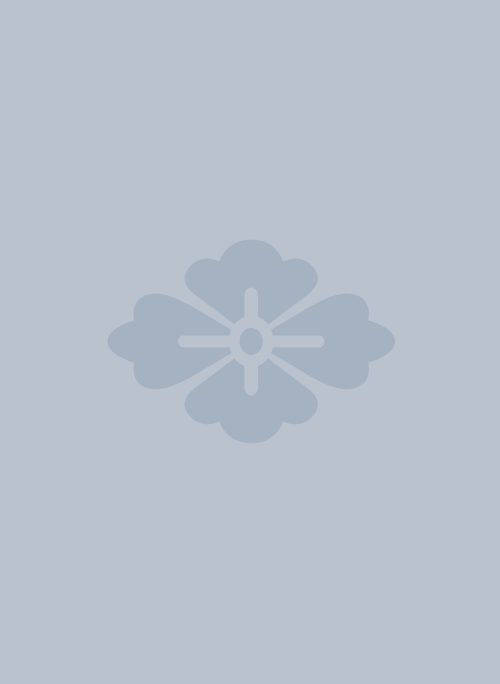「イヴァン行き、中止するのですか?」
隊長が出て行った後で、メリクがラスの傍に来て言った。
ラスはちら、とメリクを見上げる。
血まみれの部屋を掃除していたのに、いつもと変わらない。
「お前、怖くないのか?」
メリクはきょとんとする。
「あんな状況、大の男でも、部屋から逃げ出す者もいたぞ。女王は気を失ってしまったしな。普通の奴は、ああいう反応をするもんじゃないのか?」
「ラス様だって、平気だったじゃないですか」
戦に慣れた者でも、素手で相手の骨を砕くなどということは、あまりできるものではない。
剣や槍など、道具を介して手を下すのとは、訳が違うのだ。
骨を折る感触が、ダイレクトに自分にも伝わる。
決して気持ちの良いものではない。
それを顔色一つ変えずにやってのけたラスもまた、普通ではないのかもしれない。
「・・・・・・似た者同士なのかな」
呟き、メリクを見る。
イヴァンに行かなければ、という使命にも似た感覚も、おそらくメリクと同じだ。
考えてみれば、ラスのコアトルがメリクを乗せるよう、主であるラスに訴えたのだ。
普通なら、あり得ない。
他のコアトルと違って、王や世継ぎの御子のコアトルは、主と運命を共にするため、主との結びつきは何より強い。
主の意思に反することなど、するはずがないのだ。
ふぅ、と息をつき、ラスは椅子の背に頭を乗せて、目を閉じた。
考えたところで、わからない。
「もうさがれ」
軽く手を振って、ラスはメリクを追い出した。
隊長が出て行った後で、メリクがラスの傍に来て言った。
ラスはちら、とメリクを見上げる。
血まみれの部屋を掃除していたのに、いつもと変わらない。
「お前、怖くないのか?」
メリクはきょとんとする。
「あんな状況、大の男でも、部屋から逃げ出す者もいたぞ。女王は気を失ってしまったしな。普通の奴は、ああいう反応をするもんじゃないのか?」
「ラス様だって、平気だったじゃないですか」
戦に慣れた者でも、素手で相手の骨を砕くなどということは、あまりできるものではない。
剣や槍など、道具を介して手を下すのとは、訳が違うのだ。
骨を折る感触が、ダイレクトに自分にも伝わる。
決して気持ちの良いものではない。
それを顔色一つ変えずにやってのけたラスもまた、普通ではないのかもしれない。
「・・・・・・似た者同士なのかな」
呟き、メリクを見る。
イヴァンに行かなければ、という使命にも似た感覚も、おそらくメリクと同じだ。
考えてみれば、ラスのコアトルがメリクを乗せるよう、主であるラスに訴えたのだ。
普通なら、あり得ない。
他のコアトルと違って、王や世継ぎの御子のコアトルは、主と運命を共にするため、主との結びつきは何より強い。
主の意思に反することなど、するはずがないのだ。
ふぅ、と息をつき、ラスは椅子の背に頭を乗せて、目を閉じた。
考えたところで、わからない。
「もうさがれ」
軽く手を振って、ラスはメリクを追い出した。