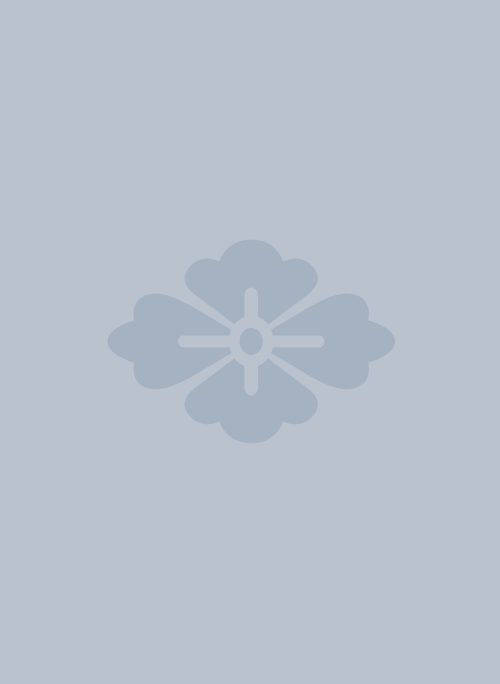ラスは寝台の上に、胡座をかいた。
「ほんとにお前は、おかしな奴だ。この顔に惹かれて寄ってきた女でも、お前ほど根気よく仕えはしないぞ。ましてお前は、まだ小さいくせに。俺など、怖いだろう」
散々冷たくあしらってきたのだ。
半年といわず、三日もあれば、根を上げるに違いない。
そう思っていたのに、メリクは決して泣き言を言わない。
時折悲しそうな目をしているのには気づいていたが、そんなことは、どうでもよかった。
トゥバンの印がなくても、一応神殿で暮らしていたのだ。
神官に泣きつくことだってできただろうに、そういったこともしない。
ラスのことを、憎む様子もないのだ。
ひたすら従順に仕えているのは、恐怖故かとも思うが、メリクはまた、ちょっと首を傾げた。
「確かに、無言の威圧感は気詰まりですけど、怖いのとは、ちょっと違うかも。嫌われたくないというか。いえ、もう嫌われているのですけど・・・・・・」
ごにょごにょと言い、最後は語尾が小さくなる。
---嫌いではない---
ふと口を突いて出そうになった言葉を、ラスは呑み込んだ。
「ほんとにお前は、おかしな奴だ。この顔に惹かれて寄ってきた女でも、お前ほど根気よく仕えはしないぞ。ましてお前は、まだ小さいくせに。俺など、怖いだろう」
散々冷たくあしらってきたのだ。
半年といわず、三日もあれば、根を上げるに違いない。
そう思っていたのに、メリクは決して泣き言を言わない。
時折悲しそうな目をしているのには気づいていたが、そんなことは、どうでもよかった。
トゥバンの印がなくても、一応神殿で暮らしていたのだ。
神官に泣きつくことだってできただろうに、そういったこともしない。
ラスのことを、憎む様子もないのだ。
ひたすら従順に仕えているのは、恐怖故かとも思うが、メリクはまた、ちょっと首を傾げた。
「確かに、無言の威圧感は気詰まりですけど、怖いのとは、ちょっと違うかも。嫌われたくないというか。いえ、もう嫌われているのですけど・・・・・・」
ごにょごにょと言い、最後は語尾が小さくなる。
---嫌いではない---
ふと口を突いて出そうになった言葉を、ラスは呑み込んだ。