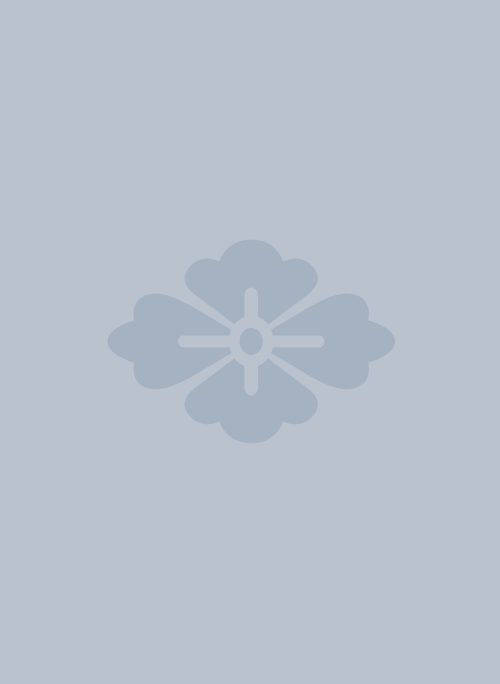甲板に出ると、少し冷たい風が吹き付ける。
日が落ちつつある朱色の空を眺めながら、ラスは誰もいない甲板を歩き、船尾に向かった。
「寒くないか?」
船尾付近に寝そべっていたラスのコアトルに、声をかける。
コアトルはエルタニンにしかいない種である。
気候が変わることが心配であったが、何となく、大丈夫だという確信があった。
伝承に過ぎない、イヴァン帝国に伝わる『氷の美姫』の話によるものだが。
イヴァン帝国のどこかに、氷の中に封じられた姫君がいるというのだ。
姫については、魔女であったために氷漬けの刑に処されたとか、神に愛されすぎて、形を残したまま天に召されたのだとか、諸説あるのだが、その中に、『氷の美姫は、エルタニン王国の王女である』という説があったのだ。
その証拠に、姫の封じられている氷の柱は、コアトルによって守られているという。
氷の美姫の伝承自体が、真実味の薄いものだが、何故だかラスは、その伝承に確信めいたものを感じたのだ。
氷の美姫がエルタニンの王女で、コアトルが守っている、ということまでは真実とも思えないが、少なくとも、イヴァンでもコアトルは生きられるであろう、と。
「何でかねぇ。お前、実はイヴァンの産まれなのか?」
コアトルの頭を撫でながら、何気なく呟く。
コアトルは答えるでもなく、ラスに頭を擦りつけた。
風の吹き抜ける甲板は寒い。
なるほど、ここでこれほどの寒さなら、一旦ルッカサに立ち寄るのも頷ける。
ラスは外套を引き上げた。
日が落ちつつある朱色の空を眺めながら、ラスは誰もいない甲板を歩き、船尾に向かった。
「寒くないか?」
船尾付近に寝そべっていたラスのコアトルに、声をかける。
コアトルはエルタニンにしかいない種である。
気候が変わることが心配であったが、何となく、大丈夫だという確信があった。
伝承に過ぎない、イヴァン帝国に伝わる『氷の美姫』の話によるものだが。
イヴァン帝国のどこかに、氷の中に封じられた姫君がいるというのだ。
姫については、魔女であったために氷漬けの刑に処されたとか、神に愛されすぎて、形を残したまま天に召されたのだとか、諸説あるのだが、その中に、『氷の美姫は、エルタニン王国の王女である』という説があったのだ。
その証拠に、姫の封じられている氷の柱は、コアトルによって守られているという。
氷の美姫の伝承自体が、真実味の薄いものだが、何故だかラスは、その伝承に確信めいたものを感じたのだ。
氷の美姫がエルタニンの王女で、コアトルが守っている、ということまでは真実とも思えないが、少なくとも、イヴァンでもコアトルは生きられるであろう、と。
「何でかねぇ。お前、実はイヴァンの産まれなのか?」
コアトルの頭を撫でながら、何気なく呟く。
コアトルは答えるでもなく、ラスに頭を擦りつけた。
風の吹き抜ける甲板は寒い。
なるほど、ここでこれほどの寒さなら、一旦ルッカサに立ち寄るのも頷ける。
ラスは外套を引き上げた。