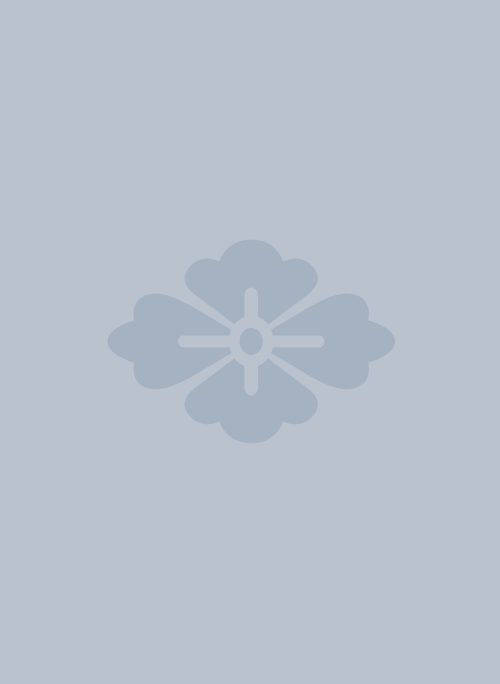「でも、最終的な王印は、ラス様が押してますね。ラス様、行くの、承諾したのですか?」
「ああ。この王宮にいたって、つまらない。奴らが罠を仕掛けるなら、こっちから破ってやるさ。いい加減、うんざりだ。謀(はかりごと)をことごとく破って、最終的に奴らをひれ伏させてやる。それに、ちょっとイヴァンには、惹かれるものがある」
「あのっ」
メリクは衝動的に声を上げていた。
「わたくしも、連れて行ってください」
ラスが、驚いたようにメリクを見る。
メリク自身も、驚いていた。
王の巫女として、戦場について行く巫女もいるが、メリクは先程、巫女ではないと告白したばかりだ。
武器が使えるわけでもない。
足手まといの何物でもないが、何故かイヴァンに行きたい、という思いに突き動かされ、気がついたらラスに同行を求めていた。
「何故だ? 巫女ではないとわかったからといって、お前を守るほど、俺は優しくないぞ」
メリクは駄々っ子のように、ぶんぶんと首を振ると、ばん、と机に両手をついた。
「何故かはわかりません。でも、何故か‘行かなければ’と思うんです」
言葉にした途端、確信にかわる。
イヴァンに行く。
それは、メリクに与えられた使命だ。
「何もできませんので、もちろん守っていただかなくても構いません。同行させていただくだけで結構です。お願いです」
机の向こうから訴えるメリクを、しばらくじっと見つめていたラスは、少し考えると、ぽつりと呟いた。
「勝手にするがいい」
「ああ。この王宮にいたって、つまらない。奴らが罠を仕掛けるなら、こっちから破ってやるさ。いい加減、うんざりだ。謀(はかりごと)をことごとく破って、最終的に奴らをひれ伏させてやる。それに、ちょっとイヴァンには、惹かれるものがある」
「あのっ」
メリクは衝動的に声を上げていた。
「わたくしも、連れて行ってください」
ラスが、驚いたようにメリクを見る。
メリク自身も、驚いていた。
王の巫女として、戦場について行く巫女もいるが、メリクは先程、巫女ではないと告白したばかりだ。
武器が使えるわけでもない。
足手まといの何物でもないが、何故かイヴァンに行きたい、という思いに突き動かされ、気がついたらラスに同行を求めていた。
「何故だ? 巫女ではないとわかったからといって、お前を守るほど、俺は優しくないぞ」
メリクは駄々っ子のように、ぶんぶんと首を振ると、ばん、と机に両手をついた。
「何故かはわかりません。でも、何故か‘行かなければ’と思うんです」
言葉にした途端、確信にかわる。
イヴァンに行く。
それは、メリクに与えられた使命だ。
「何もできませんので、もちろん守っていただかなくても構いません。同行させていただくだけで結構です。お願いです」
机の向こうから訴えるメリクを、しばらくじっと見つめていたラスは、少し考えると、ぽつりと呟いた。
「勝手にするがいい」