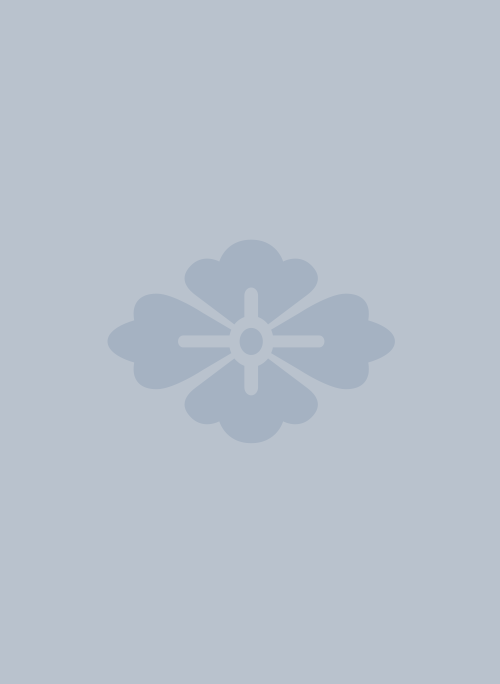「し、神殿に仕える、力ある巫女と、何の力もない単なる女子(おなご)とでも、神殿の人間ではない、というだけで、ラス様はただの女子(おなご)のほうを選びますか?」
隠しようもないほど震える声で、メリクはラスに問うた。
このようなことを聞いて、どうしようというのか、自分でもわからない。
が、勝手に口から言葉がこぼれてしまう。
一度口から出てしまえば、もうどうしようもない。
メリクは震えながら、ラスを見つめた。
無視されることも覚悟の上だったが、ラスは手に持っていた書類を机に投げ出すように置くと、頬杖をついて、口を開いた。
「そうだな。大体俺は、神官や巫女などという存在は、端(はな)から信用していない。神託などというものも、所詮は神官や巫女の口から聞くものだ。奴らが‘神託だ’と言えば、奴らの言葉が神託になる。そんな曖昧なもの、信じられるものか」
ラスの言うことも、もっともだ。
長く神殿に仕えていたメリクでさえ、神官や巫女が、本当に神の声を聞くことができるのか、疑問に思うことがある。
神官全員がそういうわけではないのかもしれないが、どう考えても己に利のある神託しか、上に報告しない者もいるのだ。
そのようなもの、本当に神託なのだろうか?
「おかしなことを聞く奴だな。俺が神殿を毛嫌いしているのは、嫌と言うほど身に染みているだろうに」
両手をぎゅっと握り、唇を引き結んでいるメリクを、ラスは見上げた。
初めてまともに目が合う。
隠しようもないほど震える声で、メリクはラスに問うた。
このようなことを聞いて、どうしようというのか、自分でもわからない。
が、勝手に口から言葉がこぼれてしまう。
一度口から出てしまえば、もうどうしようもない。
メリクは震えながら、ラスを見つめた。
無視されることも覚悟の上だったが、ラスは手に持っていた書類を机に投げ出すように置くと、頬杖をついて、口を開いた。
「そうだな。大体俺は、神官や巫女などという存在は、端(はな)から信用していない。神託などというものも、所詮は神官や巫女の口から聞くものだ。奴らが‘神託だ’と言えば、奴らの言葉が神託になる。そんな曖昧なもの、信じられるものか」
ラスの言うことも、もっともだ。
長く神殿に仕えていたメリクでさえ、神官や巫女が、本当に神の声を聞くことができるのか、疑問に思うことがある。
神官全員がそういうわけではないのかもしれないが、どう考えても己に利のある神託しか、上に報告しない者もいるのだ。
そのようなもの、本当に神託なのだろうか?
「おかしなことを聞く奴だな。俺が神殿を毛嫌いしているのは、嫌と言うほど身に染みているだろうに」
両手をぎゅっと握り、唇を引き結んでいるメリクを、ラスは見上げた。
初めてまともに目が合う。