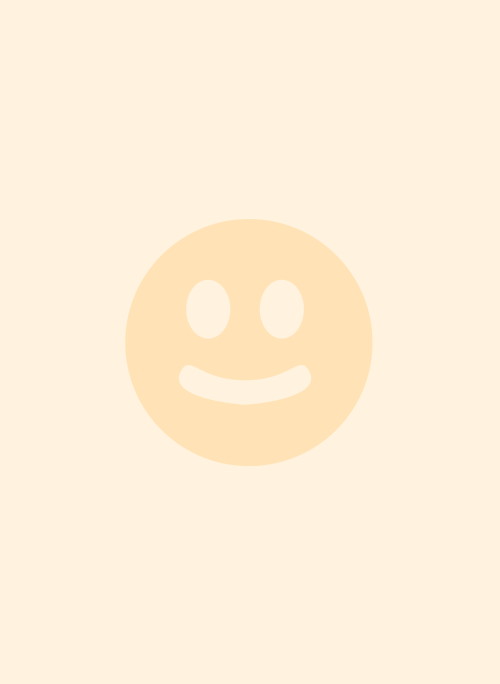「秀の家に泊まっちゃダメ?」
「ダメに決まってるだろ」
「……だよね」
奈菜は小さく微笑んで
「じゃあ、秀の家に一番近い駅で降ろして?」
と言った。
「どうするんだ?」
「駅前ならビジネスホテルくらいあるでしょ?」
「一人で泊まるのか?」
奈菜は“だって他に誰もいないでしょ?”と笑い“秀が心配するような事はしないから”と続けた。
「でもな……」
煮え切らない僕に奈菜は
「一晩くらい私だって大丈夫なんだから。これでも一応、高校生だよ。子どもじゃないよ」
と明るく話した。
車はもう30分以上も止まったまま。
雨の強さは激しさを増していた。
「秀、手を繋いでもいい?」
僕が手を出すと、奈菜の手が重なる。
「奈菜、寒い?」
僕の手に置かれた奈菜の手は冷たかった。
「なんで?丁度いいよ」
「奈菜の手、冷たい」
「そう?秀の手は温かいよね」
奈菜は重ねられただけの僕の手を握った。
「そう言えば、秀は知ってる?
手が冷たい人はね、心が温かいんだよ」
「じゃあ、僕の心は冷たい?」
奈菜は首を横に振って言った。
「手が冷たい私には、温かい秀の手が必要なの。
だから、ずっとこの手を温めていてね」