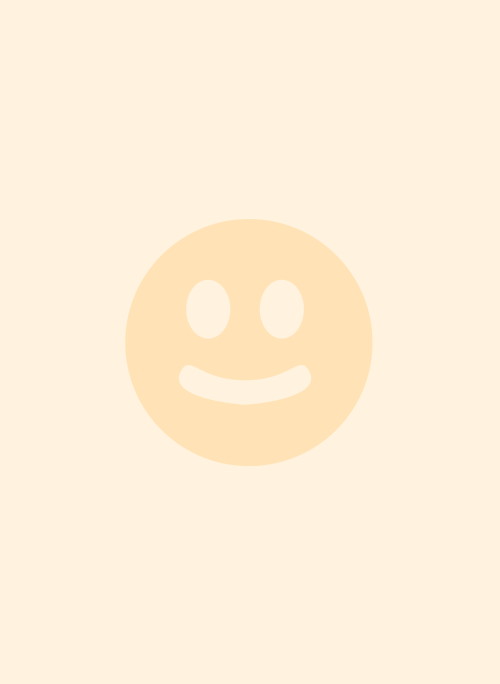速いリズムを刻んで遠ざかっていく玲香のヒールの音。
それが聞こえなくなって、しばらくして
僕はベッドから重い腰を上げ、寝室のクローゼットを開けた。
そこで、今夜、玲香に渡す筈だった、綺麗にラッピングが施されている小さな箱を手に取って、リビングへ向かうと、
キッチンに置いてあるゴミ袋に叩きつけるようにそれを捨て、
まだ温かい鍋の中身を流し込んだ。
その翌日から、玲香は毎日のように電話をかけてきた。
しかし、今の僕はとてもじゃないが、冷静に話せる自信はない。
だから、それを無視し続けた。
それから一週間が過ぎ、
ある日、僕が仕事から帰ると、玄関の前に玲香が立っていた。
「秀平とちゃんと話がしたい」
今にも溢れ出そうな涙を瞳一杯に溜めて、玲香は訴えるような眼差しを僕に向けた。
「今更なにを話すんだ?
僕が玲香の言い訳を聞けばいいのか?」
玲香は首を横に振った。
「じゃあ何?」
僕が事務的に尋ねると、
多分、我慢できなくなったであろう玲香の涙が零れた。
僕は鍵を開けると仕方なく、玲香を部屋に通した。
ソファーに座り、鞄から出したハンカチで目を押さえる玲香。
僕はその様子を見ながら
「話したい事ってなに?」
と、ぶっきらぼうに尋ねる。
僕はもう玲香に優しくしてやることなんて出来なかった。
「ごめんなさい」
玲香は再び溢れる涙を拭いて、目を押さえた。
「もう、そんな事どうでもいいよ」
「…でも……」
「だってもう、終わりだろ?」
当たり前のように言い放った僕の一言に
玲香は目に当てていたハンカチを外し、大きな瞳から溢れ、頬を伝う涙をそのままに力無く呟いた。
「…秀…平」