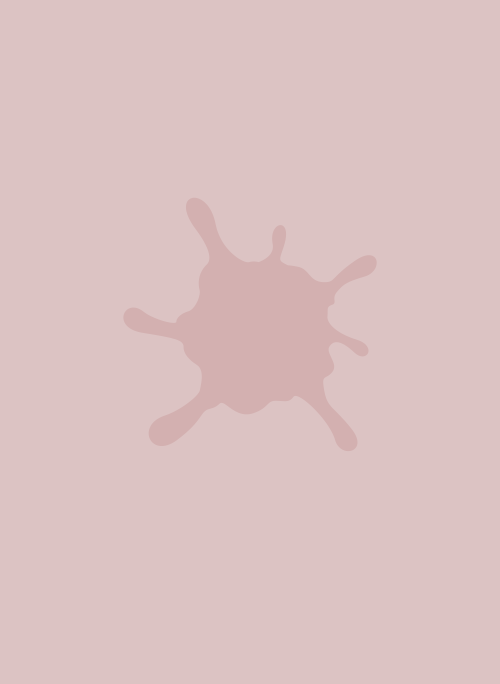おれは思い出せなかった。母親がゴソゴソと冷凍室の中をかき回しているときも。
「あった」
霜が付着して茶色が霞んでいるビニール袋を自慢げに電子レンジに入れたときも。
「ちょっと待ってね」
ピィーと解凍終了の合図をした電子レンジからそれを取り出したときも。
「変な臭いがするわ」
怪訝な顔でまな板の上にのせ、朽木を粉状に砕いたカブトムシ専用マットを破けたビニールの穴に指で母親が突いているときも鮮度の落ちた牛肉しか見えなかった。
「きゃー」
母親が絶叫したときようやく夏の思い出が解凍された。
素直に謝るか笑ってごまかそうかと迷っているうちに、父親と兄貴の冷たい視線が突き刺さる。
虫に限らずお祭りで売られている生き物ならひと通り買ってしまうおれを疑わないほうがおかしい。
それからのおれは家族の中で浮いた存在となり、奇人変人扱いされることとなった。
人生の汚点第一号の出来事。
カブトムシが死んだ悲しみの記憶は汚れてしまった。
おれの心も汚れた。犬や猫の死を何度も目の当たりにするようになってから死を悼み、嘆くことを忘れてしまった気がする。
2100円。それが彼らの命の値段。
病気や高齢、やむ得ない事情で飼えなくなった犬や猫を保健所に連れてきて処分するときにかかる手数料がその金額。
電話で処分をお願いしてきた飼い主に手数料がかかることを告げると大概の人は一瞬の沈黙のあと「かまいません」と渋々OKする。
どれだけの葛藤があったのか知る由もないが、電話した手前仕方なく了承したという心境が窺える。
「あった」
霜が付着して茶色が霞んでいるビニール袋を自慢げに電子レンジに入れたときも。
「ちょっと待ってね」
ピィーと解凍終了の合図をした電子レンジからそれを取り出したときも。
「変な臭いがするわ」
怪訝な顔でまな板の上にのせ、朽木を粉状に砕いたカブトムシ専用マットを破けたビニールの穴に指で母親が突いているときも鮮度の落ちた牛肉しか見えなかった。
「きゃー」
母親が絶叫したときようやく夏の思い出が解凍された。
素直に謝るか笑ってごまかそうかと迷っているうちに、父親と兄貴の冷たい視線が突き刺さる。
虫に限らずお祭りで売られている生き物ならひと通り買ってしまうおれを疑わないほうがおかしい。
それからのおれは家族の中で浮いた存在となり、奇人変人扱いされることとなった。
人生の汚点第一号の出来事。
カブトムシが死んだ悲しみの記憶は汚れてしまった。
おれの心も汚れた。犬や猫の死を何度も目の当たりにするようになってから死を悼み、嘆くことを忘れてしまった気がする。
2100円。それが彼らの命の値段。
病気や高齢、やむ得ない事情で飼えなくなった犬や猫を保健所に連れてきて処分するときにかかる手数料がその金額。
電話で処分をお願いしてきた飼い主に手数料がかかることを告げると大概の人は一瞬の沈黙のあと「かまいません」と渋々OKする。
どれだけの葛藤があったのか知る由もないが、電話した手前仕方なく了承したという心境が窺える。