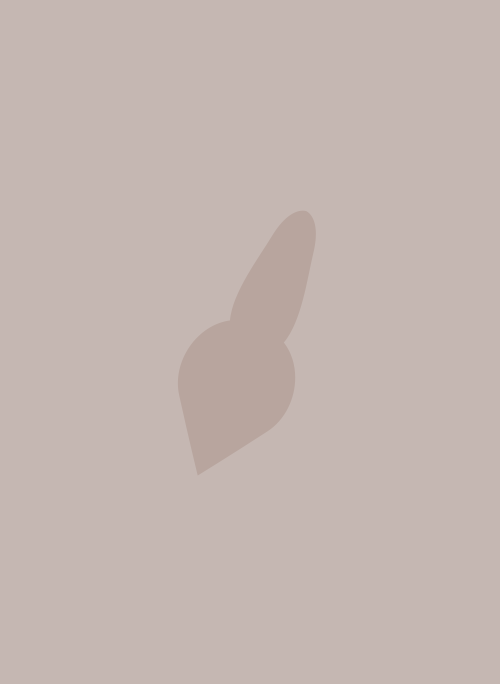「——そうだな……。時雨ちゃんの気が向いた時に俺の元に来な?何か困ったことがあれば俺が何とかしてやるよ。」
「うむ。だったらお前の元でなどと世話にならぬかもな。」
ケラケラと笑う時雨に伊藤は苦笑いを見せた。
(何とも捻くれた嬢ちゃんだ。こんなだとこの先苦労することがあるやもしれんな。)
と内心思っていたのだった。
「そもそも!長州が私のことを追いかけ回しているじゃないか。それが今困っていることだ。私は半妖である身、お前らが思っているような力は今の私は持ち合わせていない。」
分かっているとは思うが、こんな事を言った相手は長州の人間だ。
時雨を捕えようとしている理由を知っている伊藤は困った表情をした。
「それはすまなかった。だが、誰も言わぬが時雨ちゃんを捕らえる計画は実質終わっているんだよ。時雨ちゃんがどうしても欲しいと言っていた高杉と言う男が春に亡くなってしまってな、その上、嬢ちゃんを追いかけ回す程今の情勢は穏やかではない。だからもう心配することはないんだよ。」
その言葉に時雨はニコッと笑った。
「そうか……。それならば、尚、お前の世話になることなどないな。」
「……。完全に俺は振られたようだな。」
伊藤は、時雨の頭に手を置きポンポンと軽く撫でた。
「どっちにしろ、困ったことがあればこの伊藤を頼れな?」
「だから頼らないって言ってるだろ!」
「あ!そうだそうだ!一番の用を忘れるところだった!」
伊藤はヘラヘラと笑いながら袖をゴソゴソとし、スッと出てきたその手にあったのは、時雨の赤い髪紐だった。
「それ!」
時雨が驚いたように目を見開くと、伊藤は時雨の髪に結ってやった。