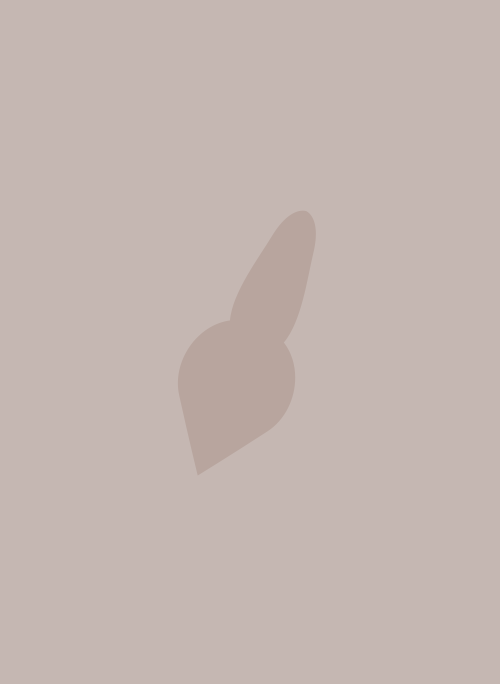「久しぶりだの~。」
「———何か用か?」
ニヤニヤしながら時雨の頭を撫でる伊藤に対し、時雨は完全に白い目を向けていた。
(何だよこの助平は……。平助と話したいのに!)
すると、ピタリと頭を撫でる手が止まった。
何事かと見上げると、伊藤が至極真面目な顔をしていた。
「時雨ちゃんよ、あんた俺と共に来ないか?」
「——は?」
いきなりの事に時雨は呆気にとられた。
しかし、どうも冗談を言っている様な雰囲気ではなかった。
時雨は気を取り直し、伊藤を見た。
「——誰が行くか、馬~鹿!」
「んなっ……!?」
時雨が発したのは何とも辛辣かつ幼稚な言葉だった。
伊藤は口元をひくつかせた。
そして、時雨の頭を鷲掴みにし、顔を寄せた。
「この伊藤の誘いを断るとは、本当に嬢ちゃん何者なんだ?」
「私は何者でもない。ただ、既に見届けると決めた奴らがいるんだ。そいつら見届けた後なら考えてやらんでもないぞ?」
時雨の暴君かの様な偉そうな発言に伊藤は吹き出してしまった。
芯の通った真っ直ぐな女だと思ったと同時に、この様な偉そうな物言いをする女も珍しいと思ったのだ。