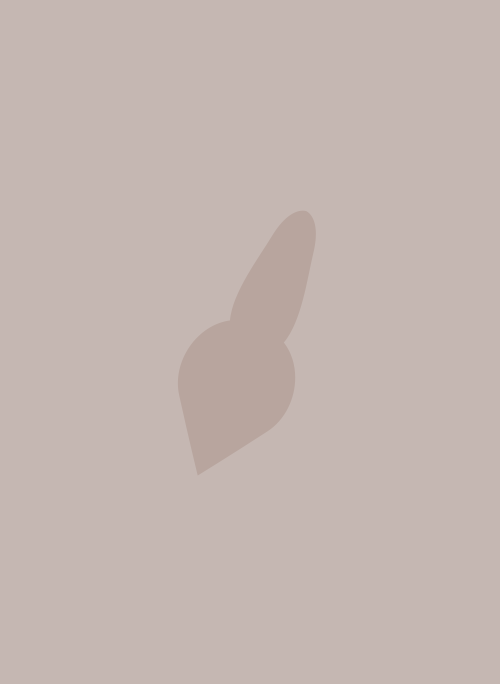頭を叩かれた山崎はぽかんとして、沖田の方を見た。
「見ました?俺、初めて母親以外の女に頭叩かれましたわ。」
頭をさすりながら襖を閉め、沖田のそばに座る山崎は些か自尊心を傷付けられていた。
そんな様子の山崎を見て沖田はケラケラ笑っていた。
「——そんなに笑わんといてくださいよ。女に頭叩かれたんですよ?しかも結構な力で!」
それを聞いた沖田はさらに大笑いした。
山崎も笑い上戸な沖田が笑出すと止まらなくなるのを知っていたため、笑いが収まるのを待った。
程なくして笑いが収まった沖田は目尻に涙を少し溜めていた。
「くくくっ……。全く、山崎君をこんなにしてしまう時雨は凄いなぁ。」
「ほんま、あの女どない神経してんねん。」
「山崎君今さっきから口調が違うね。」
「あ、すみません。少し動揺してしまいました。」
山崎はいつも、幹部隊士らには自分の国の言葉が出ない様に気を付けて話していた。
やはり、自分より上の立場の人間にはそれなりの言葉遣いが必要であると思っていたからだった。
そんな山崎に沖田はニコリ笑った。
「僕はどちらかと言えば今さっきの喋り方の方がいいな。勿論隊務などに関することであれば改めるべきだけど、ただ、普通に話す分には先程の方が気楽でいい。」
呆気に取られた山崎だったが、ふっと笑みをこぼした。
「——全くかなわんなぁ……。ほんま、あの女のせいやな。」
「あ。そういえば僕、時雨に蹴り飛ばされたんだった。」
「はぁ!?あの女ほんま何考えてんねん!!」