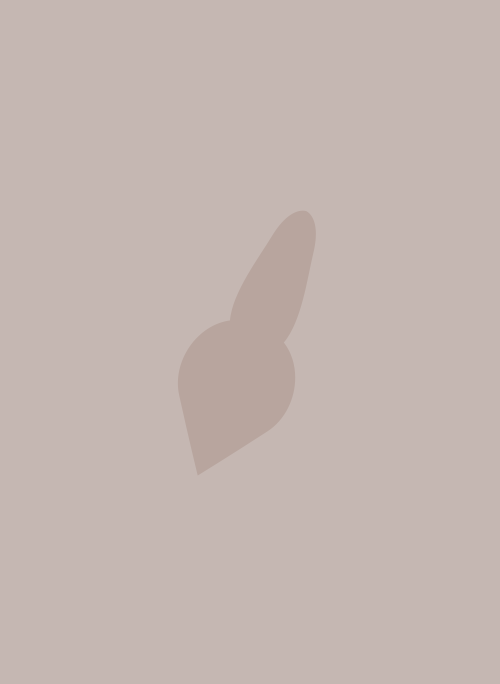「――時雨って時々かぁちゃんみてえなときあるよな……。」
「確かにな……。」
「え!?俺いつも餓鬼扱いされるんだけど!」
「「ほんとに餓鬼だからだろ。」」
そんなやり取りをされているのに気付かず、時雨は勝手場に来ていた。
「お茶お茶ー…。」
「おや、時雨さんじゃないか。」
「あ、源さん!」
ごそごそと棚を漁っていると、そこに現れたのは六番組組長の井上源三郎だった。
彼は幹部の中でも年長者であり、面倒見がよい。
そんなだから時雨も井上にすぐ懐いたのだった。
「今からお茶淹れるんですがいりますか?」
「あぁ、お願いするよ。」
そして何故か井上には敬語で話すのだ。
「じゃあ部屋に持って行きますね♪」
そう言ってニコッと笑うその笑顔は、いつもの愛想笑いや含みのある笑みとは違い、素で出るものだった。