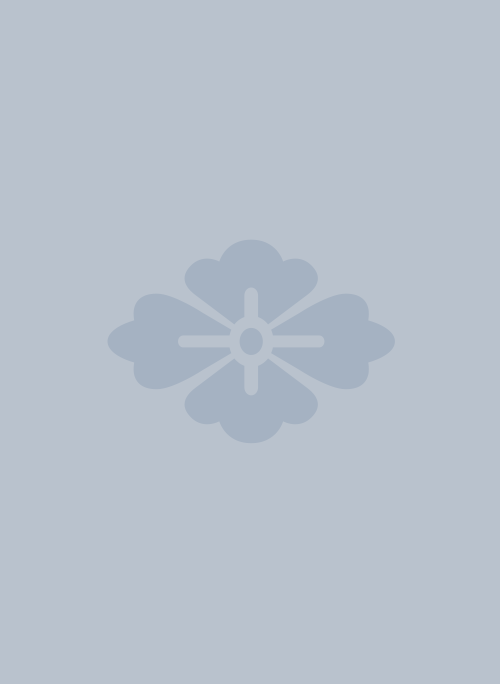そのときの美しさといったら、他にない。
小さな顔に栗色のベリーショートがよく似合っていた。
黒目がちな瞳は寝起きのせいか少し潤んでいて、やかんの蒸気を浴びた頬はほんのり色づいている。
黒いドレスから伸びる腕は陶磁器のように白く、俺は昨夜、この体を抱きかかえて夜道を歩いたのかと思うと、今さら鼓動が速くなった。
歳は、俺よりも少し上のように見えた。
俺は呼吸をするのも忘れ、仁王立ちになったまま固まった。
「あっ…あの…ごめんなさい」
鈴のような声で女が言った。
その声に我に返った俺は、小さく咳払いをして女から目を逸らした。
逸らした視線の先のダイニングテーブルには、マグカップがふたつ、置かれていた。