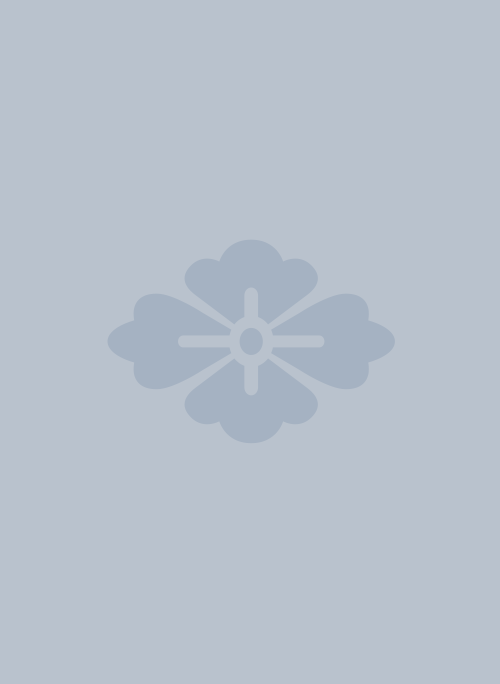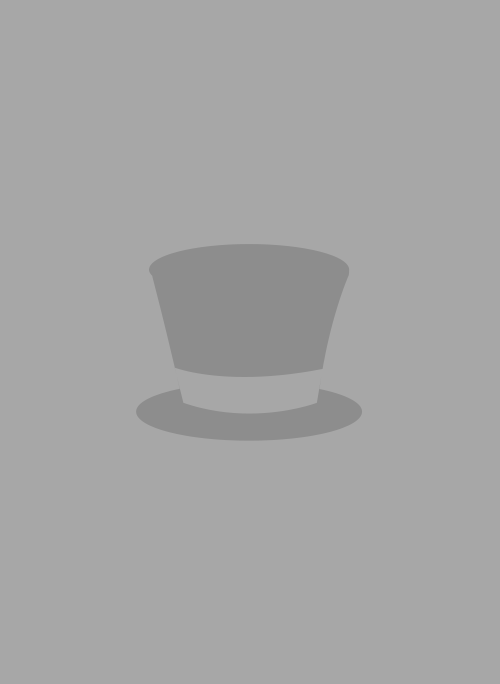翌朝、女は日が昇る直前に起きてきて、台所で湯をわかし始めた。
リビングのソファで寝ていた俺はその物音で目を覚まし、時計を見てうんざりした。
せっかくの休日に、なんでこんなに早く起こされなければならないんだ…―
そもそも、人の家(しかも誰の家だかも知らないはずだ)の台所を無断で使うなんて、どうかしてるんじゃないのか。
やっぱり連れて帰るんじゃなかった。
駅員に知らせて放っておくべきだったのに、これというのも、寒空の下で変な同情心など湧いたせいだ。
俺はムクリと起き上がって、台所の後ろ姿に向かって言った。
「…他人の家で勝手に何してるんだ」
彼女はその声に体をビクリとさせて、振り向いた。