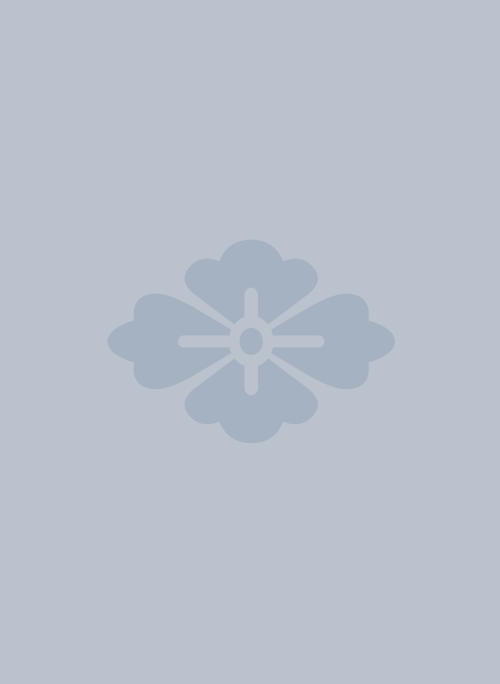「・・・・・・あの?」
「ああ、失礼致しました。いえ、剣をよく扱う、とお聞きしておりましたもので」
実際には、もっと酷いことを聞いていたのだが、そこは大人の対応で、竜が笑う。
朱夏は何と答えて良いものやら、はぁ、と間の抜けた返事をした。
「此度は夕星様とご結婚とのこと、まことにおめでとうございます。何かお気に召したものがございますれば、ささやかながら、わたくしからのお祝いとさせていただきたく思いますので、遠慮無く仰ってください」
にこにこと笑いながら、並べられた品々を指す竜に、朱夏は目を丸くした。
「いえ、でも大事な品物でしょう?」
幼い頃から市に出入りしていた朱夏は、商人にとって商品がどれほど大事なものかも、よくわかっている。
だが竜は、気にする風もなく、いろいろな宝石を広げる。
「何、他ならぬ夕星様のお相手となれば、そんなけちくさいことは、言っておれませぬよ。これなどどうです? 南の海で採れた、珍しい黒い真珠でございますよ」
柔らかそうな布から取り出したのは、親指と人差し指で作った輪っかぐらいもある真珠だった。
小さな白い真珠は見たことはあるが、こんな大きな、しかも黒光りしている真珠など初めてだ。
「ちょっと大きすぎますかね。ではこちらは? こちらは石ではないのですが、珍しいので宝石と同じ価値があるのです。琥珀と言いまして、樹脂が固まったものなのですが、こう、擦ると・・・・・・」
軽く石を擦り、朱夏の鼻先に近づける。
「わ、良い匂い」
「ああ、失礼致しました。いえ、剣をよく扱う、とお聞きしておりましたもので」
実際には、もっと酷いことを聞いていたのだが、そこは大人の対応で、竜が笑う。
朱夏は何と答えて良いものやら、はぁ、と間の抜けた返事をした。
「此度は夕星様とご結婚とのこと、まことにおめでとうございます。何かお気に召したものがございますれば、ささやかながら、わたくしからのお祝いとさせていただきたく思いますので、遠慮無く仰ってください」
にこにこと笑いながら、並べられた品々を指す竜に、朱夏は目を丸くした。
「いえ、でも大事な品物でしょう?」
幼い頃から市に出入りしていた朱夏は、商人にとって商品がどれほど大事なものかも、よくわかっている。
だが竜は、気にする風もなく、いろいろな宝石を広げる。
「何、他ならぬ夕星様のお相手となれば、そんなけちくさいことは、言っておれませぬよ。これなどどうです? 南の海で採れた、珍しい黒い真珠でございますよ」
柔らかそうな布から取り出したのは、親指と人差し指で作った輪っかぐらいもある真珠だった。
小さな白い真珠は見たことはあるが、こんな大きな、しかも黒光りしている真珠など初めてだ。
「ちょっと大きすぎますかね。ではこちらは? こちらは石ではないのですが、珍しいので宝石と同じ価値があるのです。琥珀と言いまして、樹脂が固まったものなのですが、こう、擦ると・・・・・・」
軽く石を擦り、朱夏の鼻先に近づける。
「わ、良い匂い」