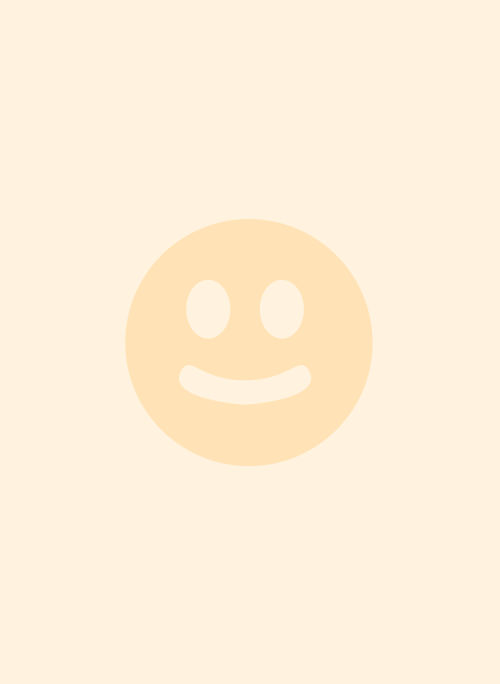そう言ってやると、幸は苦笑した。
「フッ・・・容赦ない言い方だ。貴女が叶えた恋にも、酷い話があったんだな。」
「ああ、好きな奴でも普通に捨てる人間もいたぞ。」
それを聞くと、幸は出かけた月を見上げる。
「捨てるも何も、俺は後2日で消えるんだ。」
「でも、置いていく事にはなるぞ。」
「酷いこと言うな。」
突込み気味に言うと、月から目を離して幸が生まれた家の方角に向く。
「家族が恋しいのか?」
「いや、むしろいなくてもいい。」
「何で」
「・・・・」
幸が黙る。
その時、私はあることを思い出した。幸の両親は彼が幼い頃に死亡しており、親戚もどこも引き取ってくれずに施設に行ったというらしい。
多分、友紀に惹かれたのは彼女の気が伝わっただけではなく、自分と似た存在だと見て共感しているのだろう。そして、仲良く接してくれる彼女が家族のように、彼が一番望んでいた家族を思わせたのだろう。
「自分と重ね合わせた・・・恋愛か。」
ああ、と幸は苦しそうにうめき気味の声で言う。
・・・・・・・・・
どうしよう。
そんな事をもう幸と別れた夜(一日前)から考えている。
人の命を操れるのは、イザナミやゼウスくらいしかいない。
私のような神には、そんな力は授かっていなかった。