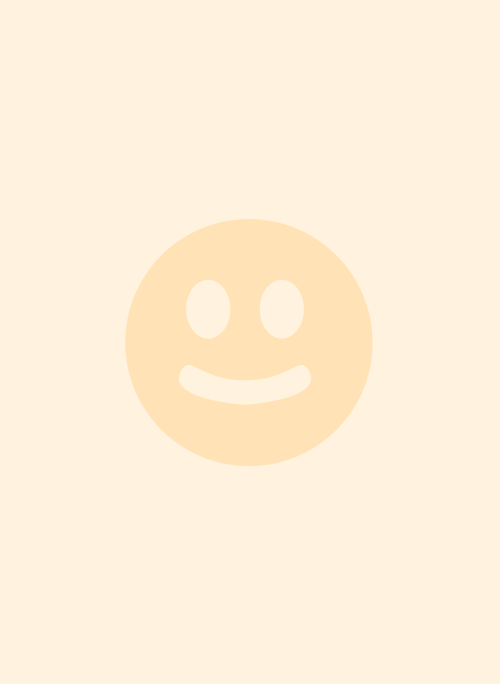「動揺してる」
「っ」
「怖いんでしょ。そう言う展開」
「冗談はよせ」
「冗談じゃないって」
秋乃が顔に書き込むなら「S」と書き込んだほうが良く似合う表情で笑っている。
「そりゃそうだよね。あたしらみたいなの、殺し屋でも守り屋でも、傷を負ってる人がそんな風にされたら、好きにもなるって」
「好きじゃない」
「頬を真っ赤にして何言ってんのよ。分かりやすい」
余計に顔が真っ赤になっていくのを、秋乃は滑稽そうに見ており、それがまた、プライドの高いリクにとっては恥ずかしいものだった。
「あんただって、そうでしょ」
「何が」
「最近、学校に行く時のリクの足取りが、妙に軽いんだもの」
「・・・そういうことなのか?」
「多分、そうよ」
妖艶に笑ってみせる秋乃だが、視線の奥にある光は、母親のような優しさを帯びていた。
話の一部始終を聞いていたエリカも、戸惑いながら壁から離れる。女子にとって「両想い」というのは嬉しいものだが、エリカはため息が出そうになる。
正直、喜べない。
好きなのは自分のほうからなだけだと思っていたし、何よりも、それが彼の重荷となってしまうのが胸を締め付けた。
邪魔でもそばにいて安心くらいさせてあげたいと、好きとは全く別の意志で今回付いてきた、今までも(いや、夏休みは違うが)そうだったのだが、まさか両想いということは分からなかったので、動揺する。
「仕事一筋」という言葉の似合いそうなリクの事だ。こんな複雑な思いは絶対に足を引っ張る事になってしまう。当然、支障が出ればもっと傷つく事にもなりかねない。
(何より、あの先生が何かとグチグチ言いそうやし)
矛盾しているのかどうかは不明だったが、そう言う面では足を引っ張りたくなかった。