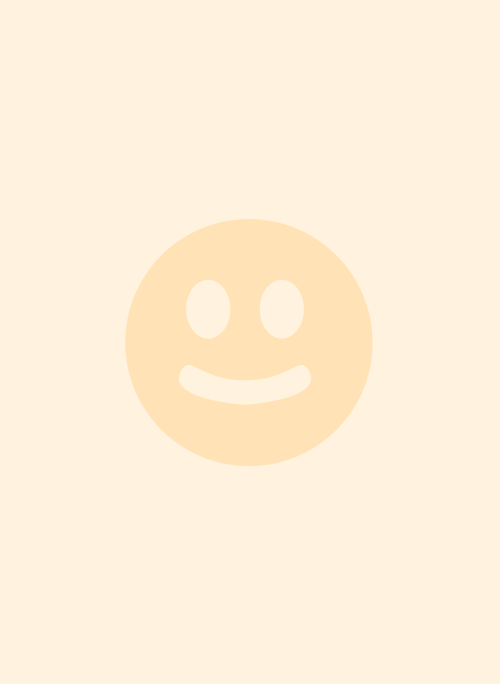「あんたが好きだからじゃないのかって聞いたら『好きなのはその次です』って即答されちゃって、こんな気分初めて」
爽快な笑みを浮かべる姿は、リクにとっても珍しかった。悪巧みをする顔しか見たことが無いからである。
すると、ん?と先ほどの秋乃の言葉を思い出す。
「好き?」
「今更?もうちょっと早く反応するかと思ったのに」
「いや・・・いかにもありえなさ過ぎて」
「悪いけど十分有り得る。ルックスもそうだけど、あんたが見せたちょっとだけ親切な所にも惹かれたんじゃない?」
「俺はそんな気を持たせるようなことしてない」
「してないつもりでも、あんたの私生活の中ではそう言うところがあったりするんだって」
「そう・・・なのか」
「ま、ルックスだけでもあんたはモテるだろうけど」
「いまいち分からない」
「そこしか見ないのは、どうせ軽い連中よ。大違いだって思うでしょ。あの子と」
「まぁな」
本当は心の底から思ってる。それは彼自身自覚している事だった。こうそっけなく答えているのは、あくまで好かれている事を『認めてはいけない』という自分のルールがあるからだ。それが自分からの好きでも、だ。
認めれば、ますます大切に思ってしまうではないか。
そんなリクに、良くか悪くか、追い討ちをかけるような言葉を繰り出す。
「両想いだね」
バッと秋乃の方を向く。「冗談はよせ、笑えない」と言いたいところだったが声が出ない。不覚にも、かなり動揺している。