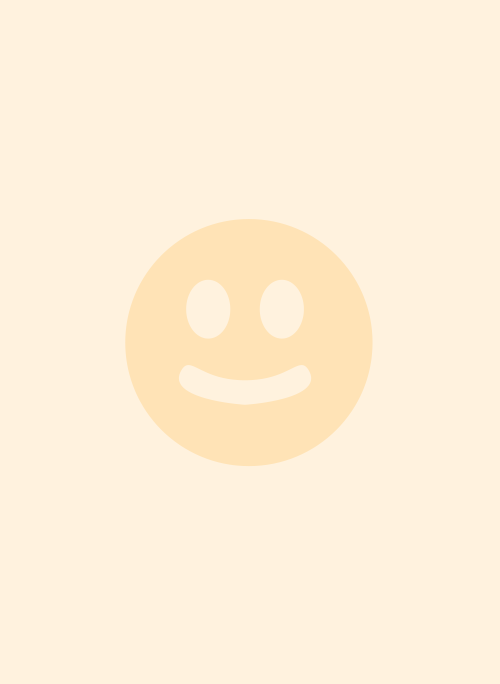すると、後ろで誰かが軽くエリカの背を叩いた。
「エーリカッ!」
「あ、美喜ちゃん。」
美喜というのは同級生の名前。
もう既に芸能界入りしている先輩のようなもの。
エリカが学校に来てからよく話している。
「もう行くの?」
「うん。そういえば美喜ちゃんは?」
「私?・・・ううん。エリカが緊張で倒れてないか見に来ただけだよっ!」
美喜の励ますやり取りはいいものだが、たった一人、リクだけはいつもより目つきを鋭くして美喜を見ていた。
じゃーね、と美喜が去って行った後、エリカは以前の明るさに戻った。
「・・・随分、優しい友達だな。」
「え?」
リクにしては珍しいことを言うので、つい変な声を出してしまう。
だが、褒めているようには聞こえない。
むしろ面倒臭そうに、そして威嚇するような声だった。
「先輩・・・それ、褒めてるんですか?」
「まあな。」
適当に答えたような声。
紙に書かれた台詞を棒読みにしたようだった。