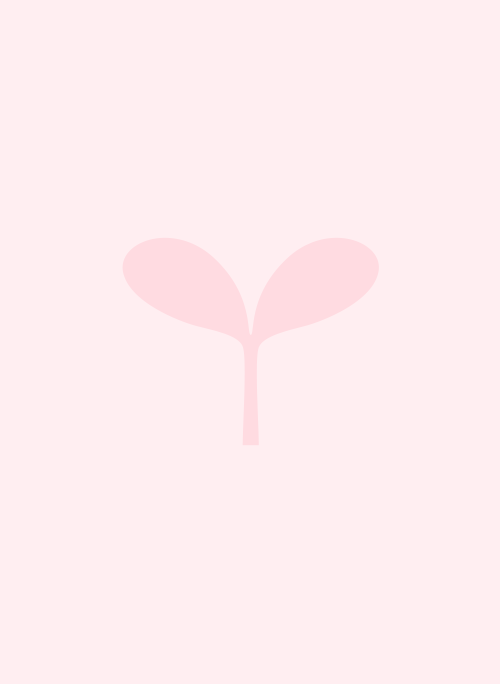痛い視線を感じたのか、親太郎は眉間にシワを寄せて困ったように笑った。
「見過ぎ」
そう言って、楽譜であたしの頭を小突いた。
「いや、だって、体調悪いのに、すごく真剣だなぁと思って」
「まぁ、唯一俺の好きなものだからな」
「だよねぇ。親太郎から音楽をとったら、何も残らないよね。よかったね、音楽と出会えて。じゃなかったら、親太郎はただのバカだもんね」
「おい、こら。ただのバカとはなんだ」
クスっと笑い合う。
「叶くんが泣いてたよ。放課後、音合わせしようと思ってたのにぃって」
はい、麦茶。 と、コップを手渡した。
「おー、サンキュ。まぁ、明日は行けんだろ」
麦茶をゴクリと飲む親太郎。
そっと、親太郎のおでこに手を伸ばす。
もう平熱に下がってるようだ。
「うん。熱は下がったみたいだね」
おでこから手を離すと、パラパラと、親太郎の前髪が落ちてきた。
「でも、明日キツければ、休みなさいよ」
「えー」
「今しっかり治さないと、体育祭出られなくなるよ」
「それは避けたいな」
「でしょ? 親太郎は昔から走るの好きだもんね」
「まぁ、ただ、お祭り騒ぎが好きなだけだけどな」
親太郎はそう言って、ウシシと笑った。
そしてまた、楽譜に視線を落とした。