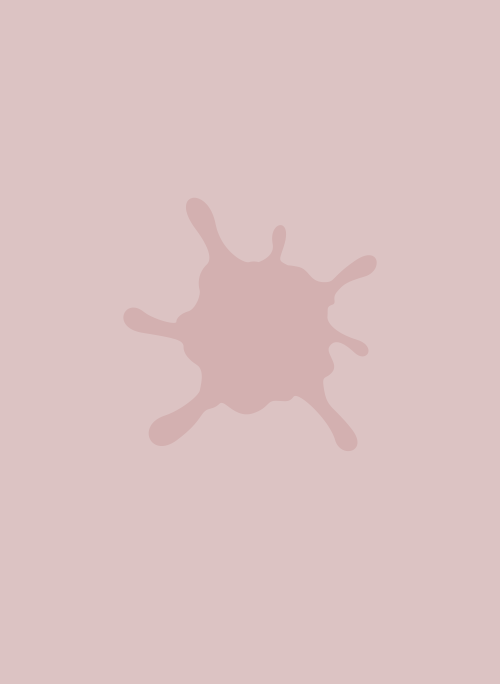部活もやってるのにすごい。
瑞穂も部活と勉強を両立している。
私は一体何やってんだろ。
中学時代、勉強が全然出来なかった私は、何を思ったのか中3から急に勉強を頑張りだし、地元じゃ有名な進学校へ入学した。
有名大学への進学率の高い超進学校と呼ばれている私立高校。
最初は憧れの制服に身を包み、これから訪れる高校生活に期待しか抱いていなかった。
しかし、入学したと同時に私はとんでもない学校へ来てしまったと後悔した。
ぎりぎりでまぐれのように合格した私が、この進学校のレベルについていけるはずがなかったのだ。
瑞穂たちと校門前で別れて、私は一人になった。
なんだろう…
なんだか重いものが体に流れてくるような…
気持ち悪い。
何これ?
「教えてあげましょうか?」
…え?
今何か声が…疲れてるのかな。
「教えてあげるわ。その感情が何なのか。」
「!」
目の前にふっと人が現れた。
金髪の髪の長い女の人。
色白で目はきれいな灰色をしている。
すいこまれそうだった。
「だれ…」
「劣等感。」
「えっ?」
「あなたが今抱いている感情の名前よぉ。」
「劣等感…」
「映してあげるねぇ。」
女の人は鏡を取り出した。
アンティーク調の細かい細工がある鏡だった。
「あなたの劣等感。」
鏡に私の姿が映る。
その瞬間、頭がくらっとして私の中から何かがすうっと抜けていく気がした。
「あ……うっ…」