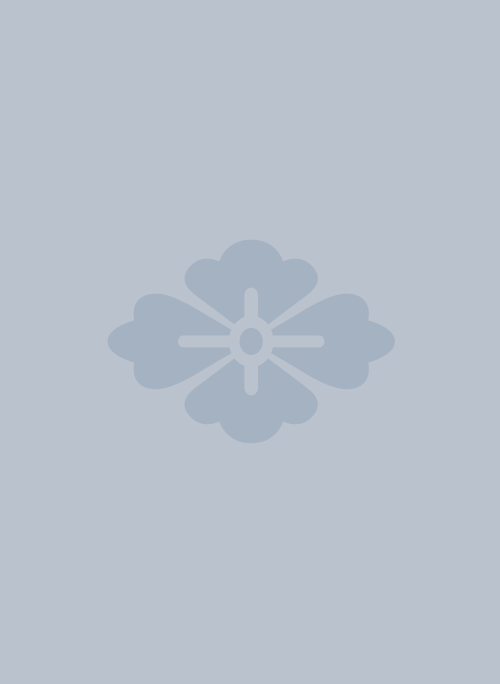俺はもう、薫が笑っていてくれれば…それで充分なんだ。
何度もその言葉を頭の中に巡らす…。そうしなければ、またあいつが現れそうだったから。
彼女の後ろ姿が行った後の視界が霞む…――――。
もう、薫は見えない。
それどころか何も見えなかった。
原因は…―――――
「止まれよ…。…っ!」
腕で瞳を思う存分押しあてた。
「止まれよ、ちくしょーっ!」
ワイシャツは訳もなく濡れ、染み込むことができなくなった水滴が溢れだした。
思いとは裏腹に【それ】は流れる。
俺は泣いた。
その水滴は涙だったんだ。溢れた涙が自然と口元をなぞる。
「―――…しょっぺぇ…。」
舌が感知して、脳が感想を述べた。
あまりにも簡単な言葉で…
あまりにもつらい、その気持ちを…。
涙と一緒に呟いた。