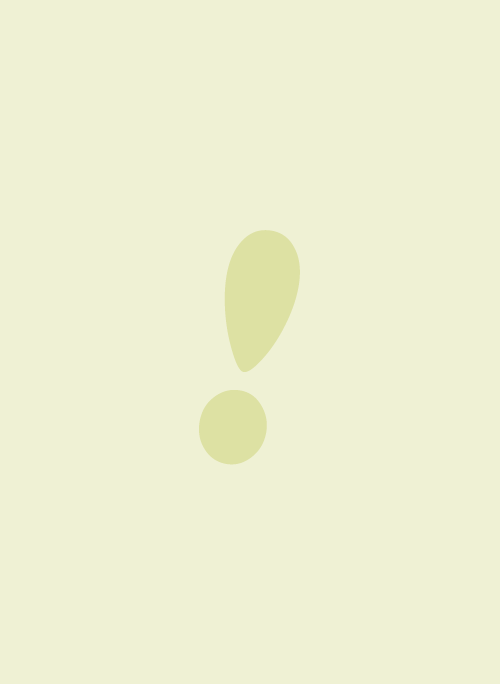しかし、突然、私を床へ落とすように胸ぐらを離し、また同じ方向へ足を進めて行った。
「異国の匂いがする女なんざ、島原にでも売ってやれ」
男性が言った言葉の後半の意味は分からない。
でも苛立ちが収まることなく行き場を失って、強く握り締めた拳に注ぎ込まれていく。
そして震えていく。
同時に強く唇を噛み締めた。
私は生粋の日本人だというのに。
江戸時代の人からしてみれば、外国人として見られてしまうんだ。
「副長!」
平助がそう声をかけるも、それさえも無視して男性は姿を消した。
ああ、言葉を自由に操れたなら……
平助の心配も私の苛立ちも、初めからなかったはずなのに。
帰る場所と言葉さえあれば、誰にも迷惑をかけずに存在できたはずのに。
どうしてもそれらを阻もうとする、目には見えない強固な壁がある。
今はその強固な壁をぶち壊す手立てがない。
「妃依ちゃん……気にすることないよ。あの人は悪い人じゃないから」
平助は私の震える両肩を掴んで、部屋へと連れていってくれた。
「異国の匂いがする女なんざ、島原にでも売ってやれ」
男性が言った言葉の後半の意味は分からない。
でも苛立ちが収まることなく行き場を失って、強く握り締めた拳に注ぎ込まれていく。
そして震えていく。
同時に強く唇を噛み締めた。
私は生粋の日本人だというのに。
江戸時代の人からしてみれば、外国人として見られてしまうんだ。
「副長!」
平助がそう声をかけるも、それさえも無視して男性は姿を消した。
ああ、言葉を自由に操れたなら……
平助の心配も私の苛立ちも、初めからなかったはずなのに。
帰る場所と言葉さえあれば、誰にも迷惑をかけずに存在できたはずのに。
どうしてもそれらを阻もうとする、目には見えない強固な壁がある。
今はその強固な壁をぶち壊す手立てがない。
「妃依ちゃん……気にすることないよ。あの人は悪い人じゃないから」
平助は私の震える両肩を掴んで、部屋へと連れていってくれた。