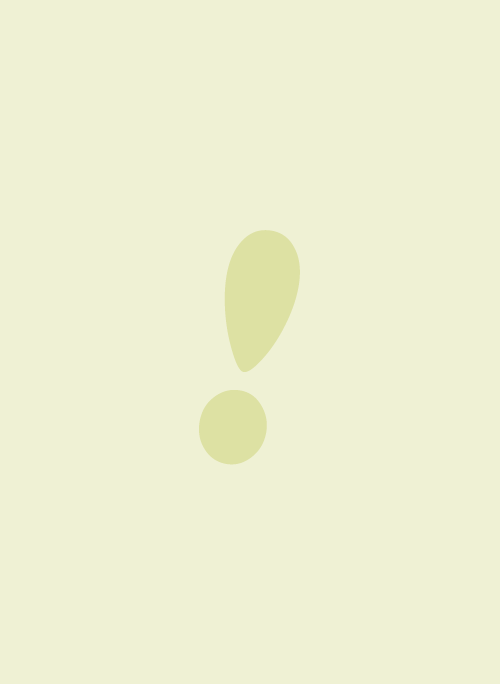“副長”と呼ばれる男性は相変わらず私をまだ睨み続けて、視線を逸らそうとしない。
負けじとこっちからも逸らしたくはなかった。
「ここに女はいらねえ。さっさと家に帰せ」
更に長く続くかと思った刹那、向こうから視線を逸らして縁側をさっさと進んで行こうとした。
それを見た私は、脳内の端の方のどこがで、何か苛立ちのようなものを覚えた。
自然と体が動いて、無造作に布団から出て男性を追いかけていく。
「妃依ちゃん!」
そう呼ばれたことも気にせず、縁側をどかどかと進み、目の前の男性の着物の袖を強く引っ張った。
瞬間、その男性は動きを止めた。
威圧がすごい。
背中からでも、殺気のようなものを感じられる。
「てめえな……」
その一言にはっとした。
だけれど、それは遅かった。
気づいた時には、すでに男性は振り向いて私の胸ぐらを掴んでいたのだから。
暫くの間、そのまま正面から睨み合いを続けた。
顔を寄せ、じっと見つめているような気がする程の。
思わず血の気が引いていく感覚に陥りそうになる。
ああ、声が出せれば良かったのに。
負けじとこっちからも逸らしたくはなかった。
「ここに女はいらねえ。さっさと家に帰せ」
更に長く続くかと思った刹那、向こうから視線を逸らして縁側をさっさと進んで行こうとした。
それを見た私は、脳内の端の方のどこがで、何か苛立ちのようなものを覚えた。
自然と体が動いて、無造作に布団から出て男性を追いかけていく。
「妃依ちゃん!」
そう呼ばれたことも気にせず、縁側をどかどかと進み、目の前の男性の着物の袖を強く引っ張った。
瞬間、その男性は動きを止めた。
威圧がすごい。
背中からでも、殺気のようなものを感じられる。
「てめえな……」
その一言にはっとした。
だけれど、それは遅かった。
気づいた時には、すでに男性は振り向いて私の胸ぐらを掴んでいたのだから。
暫くの間、そのまま正面から睨み合いを続けた。
顔を寄せ、じっと見つめているような気がする程の。
思わず血の気が引いていく感覚に陥りそうになる。
ああ、声が出せれば良かったのに。