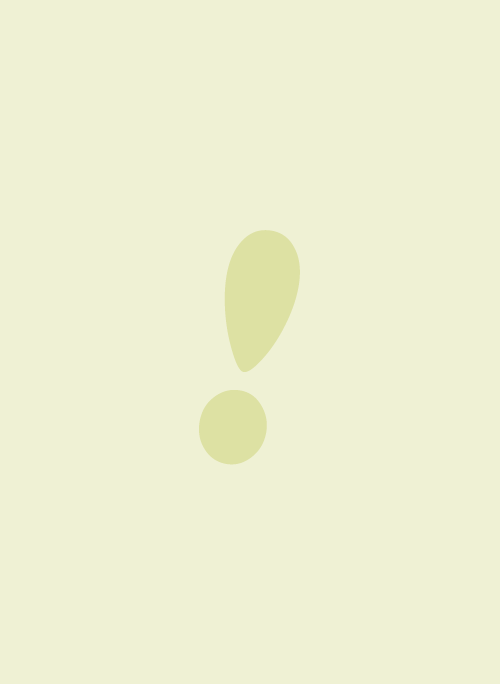まずは名前っと。
楷書ではどこかおかしいような気がするから、少し崩して行書で書く。
『村瀬妃依と申します』
一文字書き終えるごとに、藤堂平助はそれを音読していく。
「村、瀬、妃……?」
『妃依』が『ひより』と読めないんだな、と悟って、横にふりがなをふる。
「妃依ちゃんか!可愛いね」
名前が可愛いと言われたのは初めてだった。
しかも笑顔で。
徐々に顔が熱くなっていくのが、自分で分かった。
この状況から逃げるように急いで、『貴方の名は』と書き足す。
「ああ!じゃあ、筆貸して」
私の表情には全く気づいていないようで、上手く逃げ切れたようだ。
筆を渡すと、私が持つ紙にすらすらと書いていく。
書き終えると筆を私に返し、軽く咳払いをしてはしっかりと正座した。
「改めまして、俺は藤堂平助。よろしくね」
私を見つめてそう言い終えると、にこっと微笑み、さらに私を見つめ続ける。
その時間は長く続いているのかもしれないけれど、不思議と私は目をそらせなかった。
何故だか、心の奥底が怪我をしたように疼いているんだ。
楷書ではどこかおかしいような気がするから、少し崩して行書で書く。
『村瀬妃依と申します』
一文字書き終えるごとに、藤堂平助はそれを音読していく。
「村、瀬、妃……?」
『妃依』が『ひより』と読めないんだな、と悟って、横にふりがなをふる。
「妃依ちゃんか!可愛いね」
名前が可愛いと言われたのは初めてだった。
しかも笑顔で。
徐々に顔が熱くなっていくのが、自分で分かった。
この状況から逃げるように急いで、『貴方の名は』と書き足す。
「ああ!じゃあ、筆貸して」
私の表情には全く気づいていないようで、上手く逃げ切れたようだ。
筆を渡すと、私が持つ紙にすらすらと書いていく。
書き終えると筆を私に返し、軽く咳払いをしてはしっかりと正座した。
「改めまして、俺は藤堂平助。よろしくね」
私を見つめてそう言い終えると、にこっと微笑み、さらに私を見つめ続ける。
その時間は長く続いているのかもしれないけれど、不思議と私は目をそらせなかった。
何故だか、心の奥底が怪我をしたように疼いているんだ。