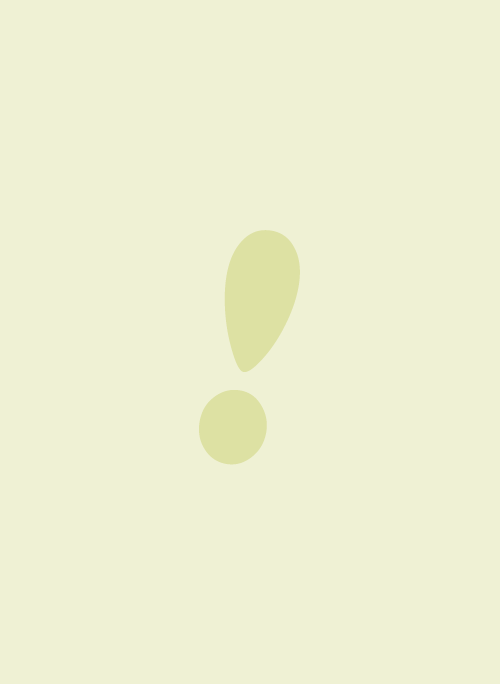声が出せないって、こんなに辛いことだったなんて、知らなかった。
声の分を表情や動きで、自分の伝えたいことを表現しなければならないなんて。
「あ、ごめん……」
俯いた私を見て、藤堂平助は申し訳なさそうにすぐに謝ってきた。
その様子に私は戸惑い、すぐに顔を上げ、頭を横にぶんぶんと振る。
別に貴方が悪いわけじゃない、と思いを込めて。
「大丈夫なら、良かった」
息を吐き肩を落として、彼はそう言った。
そんな時、ふとある物が頭を過ぎった。
ジェスチャーで伝えられるかどうか、自分の能力に賭けて、藤堂平助の肩を軽く叩く。
すぐに私の顔を見て、「何?」と言うように首を傾げた。
『何か書くものはありますか?』
口をそう動かし、手で何かを書くような振りをする。
暫く、藤堂平助は私の口と手を交互に見ていたが、ようやく理解したのか、ああ、と手を叩いた。
「筆と硯と紙ならあるよ。じゃ、持ってくるね!」
はい、と言うように私が笑顔で頷くと、彼は障子を開け急いでどこかへ向かった。
声の分を表情や動きで、自分の伝えたいことを表現しなければならないなんて。
「あ、ごめん……」
俯いた私を見て、藤堂平助は申し訳なさそうにすぐに謝ってきた。
その様子に私は戸惑い、すぐに顔を上げ、頭を横にぶんぶんと振る。
別に貴方が悪いわけじゃない、と思いを込めて。
「大丈夫なら、良かった」
息を吐き肩を落として、彼はそう言った。
そんな時、ふとある物が頭を過ぎった。
ジェスチャーで伝えられるかどうか、自分の能力に賭けて、藤堂平助の肩を軽く叩く。
すぐに私の顔を見て、「何?」と言うように首を傾げた。
『何か書くものはありますか?』
口をそう動かし、手で何かを書くような振りをする。
暫く、藤堂平助は私の口と手を交互に見ていたが、ようやく理解したのか、ああ、と手を叩いた。
「筆と硯と紙ならあるよ。じゃ、持ってくるね!」
はい、と言うように私が笑顔で頷くと、彼は障子を開け急いでどこかへ向かった。