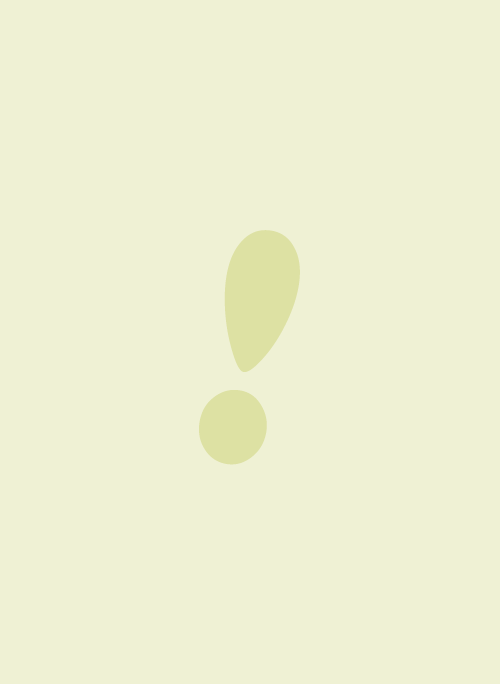「妃依ー、掃除するから早く起きてー」
ぼやっとした脳は、うっすらと明るい部屋がすでに朝を迎えていることをなんとか認識した。
原田さんの声でもなく、ましてや目覚まし時計の音でもなく、母の声に起こされる今日。
今、何時なんだろう。
どれくらい寝ていたのだろう。
そんなことも分からなくなるくらい、起きていたくなかったことは確かだ。
「はーい……」
所在なく返事をしては、もぞもぞと肌掛けの中で自分のぬくもりを探す。
ふと、パジャマの胸ポケットに手を伸ばす。
そこには、平助に去り際にもらった文をしまっていた。
いくら書道部だからといって、この文の彼の字をすべて読むことはできなかった。
昨日はそれで泣いてしまった。
彼の気持ちが今すぐに分からないだなんて、虚しすぎて。
「嫌だな……戻されるなんて」
――昨日。
父に「今は平成だよ、何言ってんだ」的なことを言われた時、気を失ったつもりでいたけれど、実際にはどうやら倒れたとかそういうことになったわけではなかったらしい。
ただ現実が遠くに感じられて、とてつもない寂しさに襲われたショックで、周りの物音が聞こえなくなっていたようだ。
しかも、日付はおろか時間もまったく進んでいなくて、父に連れられて帰ってきた時に確認したら私は夏の制服を着ていて。
“あの時”、梅雨の時期だったことも、学校帰りだったこともすっかり忘れていた。
それに、もう、あの連続した夢の更なる続きを見ることは、この先二度とないのかもしれない。
……だって今日は、久しぶりに何の夢も見ていないのだから。
ぼやっとした脳は、うっすらと明るい部屋がすでに朝を迎えていることをなんとか認識した。
原田さんの声でもなく、ましてや目覚まし時計の音でもなく、母の声に起こされる今日。
今、何時なんだろう。
どれくらい寝ていたのだろう。
そんなことも分からなくなるくらい、起きていたくなかったことは確かだ。
「はーい……」
所在なく返事をしては、もぞもぞと肌掛けの中で自分のぬくもりを探す。
ふと、パジャマの胸ポケットに手を伸ばす。
そこには、平助に去り際にもらった文をしまっていた。
いくら書道部だからといって、この文の彼の字をすべて読むことはできなかった。
昨日はそれで泣いてしまった。
彼の気持ちが今すぐに分からないだなんて、虚しすぎて。
「嫌だな……戻されるなんて」
――昨日。
父に「今は平成だよ、何言ってんだ」的なことを言われた時、気を失ったつもりでいたけれど、実際にはどうやら倒れたとかそういうことになったわけではなかったらしい。
ただ現実が遠くに感じられて、とてつもない寂しさに襲われたショックで、周りの物音が聞こえなくなっていたようだ。
しかも、日付はおろか時間もまったく進んでいなくて、父に連れられて帰ってきた時に確認したら私は夏の制服を着ていて。
“あの時”、梅雨の時期だったことも、学校帰りだったこともすっかり忘れていた。
それに、もう、あの連続した夢の更なる続きを見ることは、この先二度とないのかもしれない。
……だって今日は、久しぶりに何の夢も見ていないのだから。