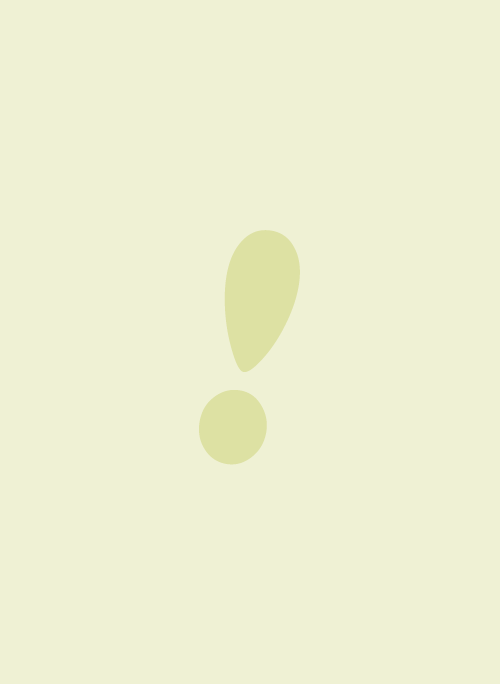もしかして、と勢い良く顔を上げて再び藤堂平助を睨む。
すると彼の頬はみるみるうちに赤く染まっていった。
つられて私も顔が熱くなる。
そしてついに彼は私から顔を逸らした。
「い、いや……別に女の子に興味があって着替えさせたわけじゃ……勘違いしないで!」
まるで私が殴るとでも思っているのかのように、手のひらを向けて両腕をこちらに伸ばしている。
鬼を恐れるみたいにして。
私は何もする気もないし、ましてや怒るにしても声が出ないんだし。
とりあえず、藤堂平助の両腕を優しく掴むことしか、今はできなかった。
「はあ、殴られるかと思ったよ……」
そう吐き出すように呟いては溜め息をついた。
「君の着てた服と持ち物なら、そこにあるから。ね?」
そう言って床の間を指差した。
確かに制服がきちんと畳まれて、バッグも置かれている。
ついでに静まり返ってしまった部屋を、ぐるりと見回す。
いかにも和室としかいいようがない。
畳、襖、床の間、掛け軸、生け花、藤堂平助と私の着物、彼の丁髷。
和の雰囲気が漂う物しか、この場にはない。
本当にここは、江戸時代なの――?
すると彼の頬はみるみるうちに赤く染まっていった。
つられて私も顔が熱くなる。
そしてついに彼は私から顔を逸らした。
「い、いや……別に女の子に興味があって着替えさせたわけじゃ……勘違いしないで!」
まるで私が殴るとでも思っているのかのように、手のひらを向けて両腕をこちらに伸ばしている。
鬼を恐れるみたいにして。
私は何もする気もないし、ましてや怒るにしても声が出ないんだし。
とりあえず、藤堂平助の両腕を優しく掴むことしか、今はできなかった。
「はあ、殴られるかと思ったよ……」
そう吐き出すように呟いては溜め息をついた。
「君の着てた服と持ち物なら、そこにあるから。ね?」
そう言って床の間を指差した。
確かに制服がきちんと畳まれて、バッグも置かれている。
ついでに静まり返ってしまった部屋を、ぐるりと見回す。
いかにも和室としかいいようがない。
畳、襖、床の間、掛け軸、生け花、藤堂平助と私の着物、彼の丁髷。
和の雰囲気が漂う物しか、この場にはない。
本当にここは、江戸時代なの――?