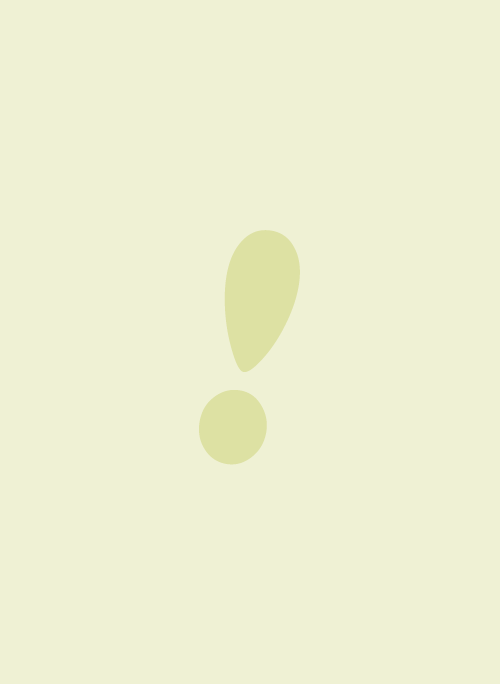花びらだって、本当は踏まれたくなんかないはずだ。
長い冬を越え、ごく僅かな期間綺麗に咲いて、後は風で散って、枯れて、そして自然に還る。
それだけの人生だから、踏まれるのは悲しくないのかな、なんて意味の分からないことを考えてみる。
そのおかげで、本心を言わなければ、という思いも、心のどこかで押さえつけられてしまった。
「どうしても……行くんだね」
やっと出た言葉がそれだった。
たったそれだけだった。
「行かないで」とは言わなかった。
あるいは、言えなかったのかもしれない。
そんな私を見るに見かねたのか何なのか、突然、ゆっくりと平助の腕がこちらに伸びてきた。
肩でも掴まれるのか、はたまた頭を撫でられるのか。
何をされるのかな、と思いつつ、少し緊張してその重みを待つ。
「……ごめん。どうしても行かなきゃならないんだ。先生に呼ばれたから……」
けれど、その手はどこにも触れることなく、戻っていってしまった。
それと同時に彼は後ろを向き、私に背を向けた。
俯いたままだった私の視界で、あるものを捉えた。
平助が拳を握りしめていたんだ。
側面から赤く見えるほど、すごい力だということが見ただけで分かった。
きっとその手は、伸ばしかけた方の手だったんだと思う。
長い冬を越え、ごく僅かな期間綺麗に咲いて、後は風で散って、枯れて、そして自然に還る。
それだけの人生だから、踏まれるのは悲しくないのかな、なんて意味の分からないことを考えてみる。
そのおかげで、本心を言わなければ、という思いも、心のどこかで押さえつけられてしまった。
「どうしても……行くんだね」
やっと出た言葉がそれだった。
たったそれだけだった。
「行かないで」とは言わなかった。
あるいは、言えなかったのかもしれない。
そんな私を見るに見かねたのか何なのか、突然、ゆっくりと平助の腕がこちらに伸びてきた。
肩でも掴まれるのか、はたまた頭を撫でられるのか。
何をされるのかな、と思いつつ、少し緊張してその重みを待つ。
「……ごめん。どうしても行かなきゃならないんだ。先生に呼ばれたから……」
けれど、その手はどこにも触れることなく、戻っていってしまった。
それと同時に彼は後ろを向き、私に背を向けた。
俯いたままだった私の視界で、あるものを捉えた。
平助が拳を握りしめていたんだ。
側面から赤く見えるほど、すごい力だということが見ただけで分かった。
きっとその手は、伸ばしかけた方の手だったんだと思う。