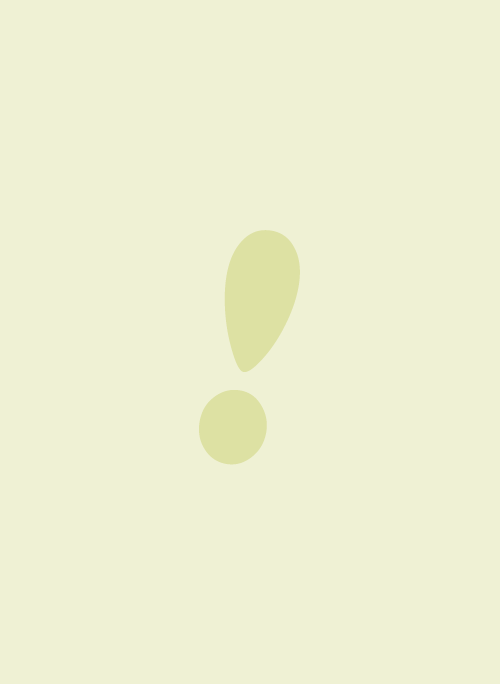私が言いたいことはそれだけじゃない。
拳をぎゅっと握る。
何を言っても平助は考えを変えないはずだ。
普段は暢気な青年というイメージがあるけれど、実は案外内で考えていそうなタイプの人間だと思う。
それだからこそ厄介だ、とも思う。
平助は私の方に向き直って、視線を交えてきた。
「何日も前に決まっていたことだけど、別に妃依ちゃんには言わなくてもいいか……って最初は思ってた。でも考え直したんだ。どうしても言わなきゃいけない気がして」
そりゃあ言ってほしいですとも、と思ってつい口に出しそうになる。
平助の存在が、私の中で"ただ私を助けてくれた恩人"というだけではないということだ。
それくらい、大きな存在なんだ。
それをたった今、実感した。
だからこそ辛いものがある。
気づいてしまったらもう、だめだ。
これからの生活が、平助のいない生活が怖い。
彼の視線から目を逸らし、俯く。
地面には桜の花びらが散らばっていて、それを踏み付ける私と平助がいる。
私はこの散った花びらみたいだな、と思い、ふっと鼻で笑う。
抱いている気持ちを無視されているような、そんな感じがして。
拳をぎゅっと握る。
何を言っても平助は考えを変えないはずだ。
普段は暢気な青年というイメージがあるけれど、実は案外内で考えていそうなタイプの人間だと思う。
それだからこそ厄介だ、とも思う。
平助は私の方に向き直って、視線を交えてきた。
「何日も前に決まっていたことだけど、別に妃依ちゃんには言わなくてもいいか……って最初は思ってた。でも考え直したんだ。どうしても言わなきゃいけない気がして」
そりゃあ言ってほしいですとも、と思ってつい口に出しそうになる。
平助の存在が、私の中で"ただ私を助けてくれた恩人"というだけではないということだ。
それくらい、大きな存在なんだ。
それをたった今、実感した。
だからこそ辛いものがある。
気づいてしまったらもう、だめだ。
これからの生活が、平助のいない生活が怖い。
彼の視線から目を逸らし、俯く。
地面には桜の花びらが散らばっていて、それを踏み付ける私と平助がいる。
私はこの散った花びらみたいだな、と思い、ふっと鼻で笑う。
抱いている気持ちを無視されているような、そんな感じがして。