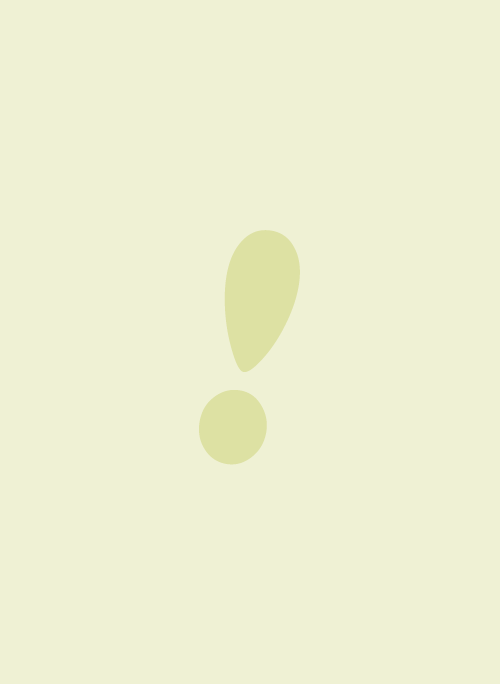春の香りのする風が吹く中、平助は少しだけ前に進んで、再び止まる。
その背中は、なんとも頼りなかった。
いつもは頼りがいがあって、出会って間もない私を優しく包み込むような包容力さえ持ち合わせている彼が、何故ここまで弱っているのだろう。
「黙ってて、ごめん。でも申し訳ないけど……妃依ちゃんを“あっち”に連れていくことはできない」
「……分かってるよ。平助はそう言うと思ってたから」
「そう……」
その声色は、とても寂しそうなものだった。
こんなことを聞いても、あの百人一首の歌の件があったから、初めから期待なんてしていなかった。
私がそう思っていることが、彼に伝わってしまったのかもしれない。
進もう、とも言わず、平助は再び歩み始めた。
それに私は何も言わずについていく。
分離する隊についていく理由については、まだ触れられていない。
ちゃんと話してくれるのだろうか、とは私は疑っていなかった。
平助ならちゃんと話してくれる。
お互いのことを色々話そう、と、一昨日茶屋で団子を食べた時に言っていたから、私はその言葉を信じているんだ。
ゆっくりと進み続けると、左手に高い白壁が見えてきた。
その上方を見ると、西本願寺のようなお寺らしき大きな建物の屋根が見えた。
本当に、昔の技術には頭が上がらない。
感動しつつ前へ向き直ると、平助も同じようにお寺らしき建物を見ていた。
その背中は、なんとも頼りなかった。
いつもは頼りがいがあって、出会って間もない私を優しく包み込むような包容力さえ持ち合わせている彼が、何故ここまで弱っているのだろう。
「黙ってて、ごめん。でも申し訳ないけど……妃依ちゃんを“あっち”に連れていくことはできない」
「……分かってるよ。平助はそう言うと思ってたから」
「そう……」
その声色は、とても寂しそうなものだった。
こんなことを聞いても、あの百人一首の歌の件があったから、初めから期待なんてしていなかった。
私がそう思っていることが、彼に伝わってしまったのかもしれない。
進もう、とも言わず、平助は再び歩み始めた。
それに私は何も言わずについていく。
分離する隊についていく理由については、まだ触れられていない。
ちゃんと話してくれるのだろうか、とは私は疑っていなかった。
平助ならちゃんと話してくれる。
お互いのことを色々話そう、と、一昨日茶屋で団子を食べた時に言っていたから、私はその言葉を信じているんだ。
ゆっくりと進み続けると、左手に高い白壁が見えてきた。
その上方を見ると、西本願寺のようなお寺らしき大きな建物の屋根が見えた。
本当に、昔の技術には頭が上がらない。
感動しつつ前へ向き直ると、平助も同じようにお寺らしき建物を見ていた。