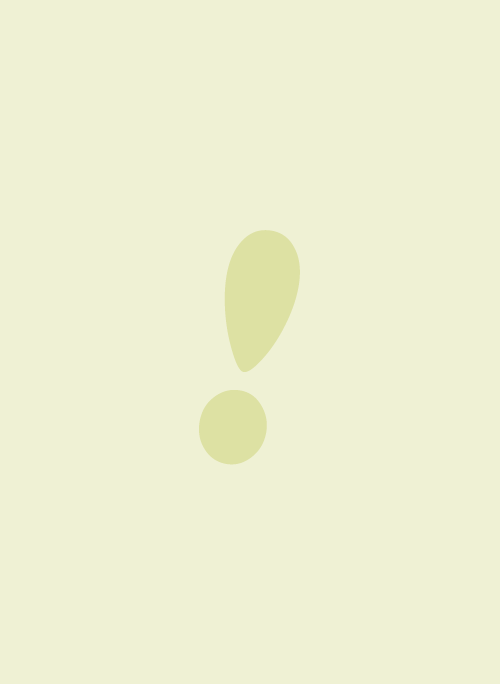「いや、大丈夫、なんだけど……」
「けど……?」
「……あ」
なんとか平助の気を他のものに移そうと思った結果、私はあることを急に思い出した。
それは、さっき私が平助と会う直前に感じた、背後からの誰かの強い視線のことだ。
彼に話しても、また心配されるだけかもしれない。
けれど、あの畏怖の念を抱くほどの瞬間のことを、タイミングはどうであれ伝えずにはいられない気分だった。
平助の気を逸らすことにもなるからちょうどいいと思ったし。
「そういえば……さっき平助と偶然会う直前、本当に直前なんだけど、後ろから誰かの視線を感じたんだ」
案の定、平助は驚いた顔をする。
何故そんなことが、と私に問いたそうな表情だ。
仮にそんなことを聞かれたとしても、私も答えようがない。
まったく身に覚えがないのだから。
「視線?……まさか、誰かに付けられてたってこと?」
「分からない……でも威圧されているような視線だったから、もしかしたらそうかもしれない。……それに、副長さんに忠告されたことも気になってて」
「え……なんて?」
「俺の部屋に頻繁に出入りするのをよく思わない奴らがいるかもしれないから、周囲にはくれぐれも気を付けるように、って。よく分からないけど」
平助の表情はどんどん曇っていくばかりだ。
彼は頭の中で、色々と思考を巡らせているんだろう。
「けど……?」
「……あ」
なんとか平助の気を他のものに移そうと思った結果、私はあることを急に思い出した。
それは、さっき私が平助と会う直前に感じた、背後からの誰かの強い視線のことだ。
彼に話しても、また心配されるだけかもしれない。
けれど、あの畏怖の念を抱くほどの瞬間のことを、タイミングはどうであれ伝えずにはいられない気分だった。
平助の気を逸らすことにもなるからちょうどいいと思ったし。
「そういえば……さっき平助と偶然会う直前、本当に直前なんだけど、後ろから誰かの視線を感じたんだ」
案の定、平助は驚いた顔をする。
何故そんなことが、と私に問いたそうな表情だ。
仮にそんなことを聞かれたとしても、私も答えようがない。
まったく身に覚えがないのだから。
「視線?……まさか、誰かに付けられてたってこと?」
「分からない……でも威圧されているような視線だったから、もしかしたらそうかもしれない。……それに、副長さんに忠告されたことも気になってて」
「え……なんて?」
「俺の部屋に頻繁に出入りするのをよく思わない奴らがいるかもしれないから、周囲にはくれぐれも気を付けるように、って。よく分からないけど」
平助の表情はどんどん曇っていくばかりだ。
彼は頭の中で、色々と思考を巡らせているんだろう。