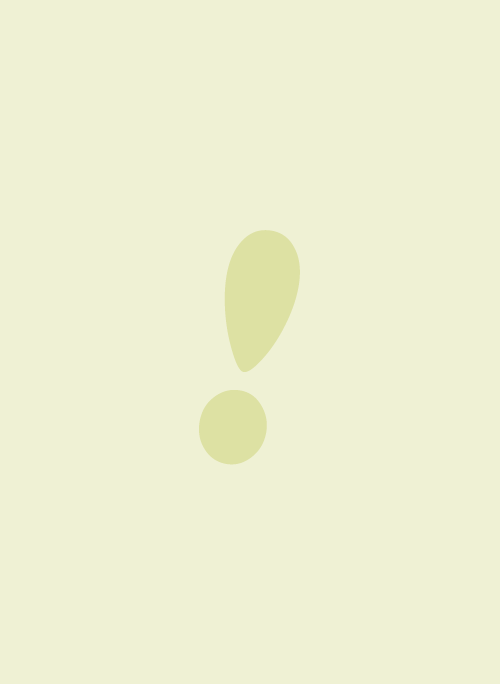隠し事があるのは、人間誰しもあっても仕方ないもの、というか、あって当たり前のものなんだと思う。
私は全てをさらけ出せないから。
だから、気にはなるけれど、隠し事をしたままの平助でいい。
捻くれた考えかもしれないけれど、その隠し事を人づてに聞いて、本人にその真相を確認した時にちゃんと話してくれればそれでいい。
……それでも私は、聞くことすら躊躇うのだけれど。
それでこそ人間くさくて、いいと思うから。
そういう人が、私はすーー
その言葉に至ってから、足を前に出すスピードを徐々に緩め、同時に顔を俯かせた。
「は……?」
そしてそう短く呟いて、唖然として立ち止まる。
瞬きもできない。
自分が、自分でも信じられない気持ちを抱いていたからだ。
“す”、だって?
ありえない、ありえない。
何を本当に思ってもいないことを考えているんだろうか、私は……近頃どうかしている……
「やっぱり調子悪い?戻る?」
突然私が止まったものだから、平助は再び心配して私を気遣いに数歩だけ戻ってきた。
はっとして顔を上げる。
聞こえていなかったらしい街の音が、一気に耳に届いてくる。
微かに吹く風の音、人の話し声、地面と草履か草鞋の擦れる音、その他諸々の生活音。
意識がどこかへいっていて、それが不意に現実に戻されたような感覚に陥る。
それはそうと、行き先は遠いのだろうか、なかなか着く気配がない。
私は全てをさらけ出せないから。
だから、気にはなるけれど、隠し事をしたままの平助でいい。
捻くれた考えかもしれないけれど、その隠し事を人づてに聞いて、本人にその真相を確認した時にちゃんと話してくれればそれでいい。
……それでも私は、聞くことすら躊躇うのだけれど。
それでこそ人間くさくて、いいと思うから。
そういう人が、私はすーー
その言葉に至ってから、足を前に出すスピードを徐々に緩め、同時に顔を俯かせた。
「は……?」
そしてそう短く呟いて、唖然として立ち止まる。
瞬きもできない。
自分が、自分でも信じられない気持ちを抱いていたからだ。
“す”、だって?
ありえない、ありえない。
何を本当に思ってもいないことを考えているんだろうか、私は……近頃どうかしている……
「やっぱり調子悪い?戻る?」
突然私が止まったものだから、平助は再び心配して私を気遣いに数歩だけ戻ってきた。
はっとして顔を上げる。
聞こえていなかったらしい街の音が、一気に耳に届いてくる。
微かに吹く風の音、人の話し声、地面と草履か草鞋の擦れる音、その他諸々の生活音。
意識がどこかへいっていて、それが不意に現実に戻されたような感覚に陥る。
それはそうと、行き先は遠いのだろうか、なかなか着く気配がない。