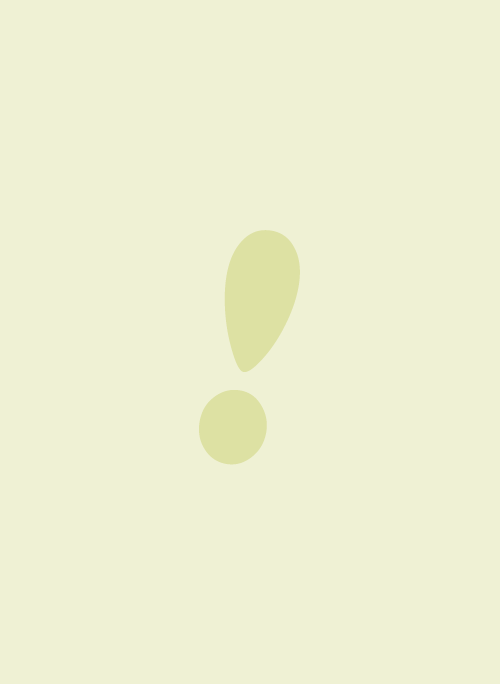紙に滲んだ墨のように、心の中にほくろのようなわだかまりができた。
きっと今の私なら、誰にも止められないだろう。
いや、今までは止める人さえいなかったけれど。
「あら、そうなの?残念だわ」
本当に残念そうに肩を落として、苑さんはそう言った。
私が帰るとなったら、彼女の動きは素早かった。
すぐに玄関に誘う。
別れを惜しむ様子もない。
旦那さんを失ってしまった苑さんにとっては、それは上辺だけなのかもしれないけれど。
下駄を履き終え、後ろを振り返る。
すると、苑さんは寂しそうな表情をしていた。
「もうここには……来ないの?」
そう言われて、はっと気づいた。
私はこの家で生活していく気でいたんだ、一昨日は。
新選組の屯所という、怖い場所から抜け出せてすっきりしていたんだ。
それなのに、今私は荷物を持ってこの家を出ていこうとしている。
きっとそんな私を見て、彼女は私がもう来ないと思ったんだろう。
きっと今の私なら、誰にも止められないだろう。
いや、今までは止める人さえいなかったけれど。
「あら、そうなの?残念だわ」
本当に残念そうに肩を落として、苑さんはそう言った。
私が帰るとなったら、彼女の動きは素早かった。
すぐに玄関に誘う。
別れを惜しむ様子もない。
旦那さんを失ってしまった苑さんにとっては、それは上辺だけなのかもしれないけれど。
下駄を履き終え、後ろを振り返る。
すると、苑さんは寂しそうな表情をしていた。
「もうここには……来ないの?」
そう言われて、はっと気づいた。
私はこの家で生活していく気でいたんだ、一昨日は。
新選組の屯所という、怖い場所から抜け出せてすっきりしていたんだ。
それなのに、今私は荷物を持ってこの家を出ていこうとしている。
きっとそんな私を見て、彼女は私がもう来ないと思ったんだろう。