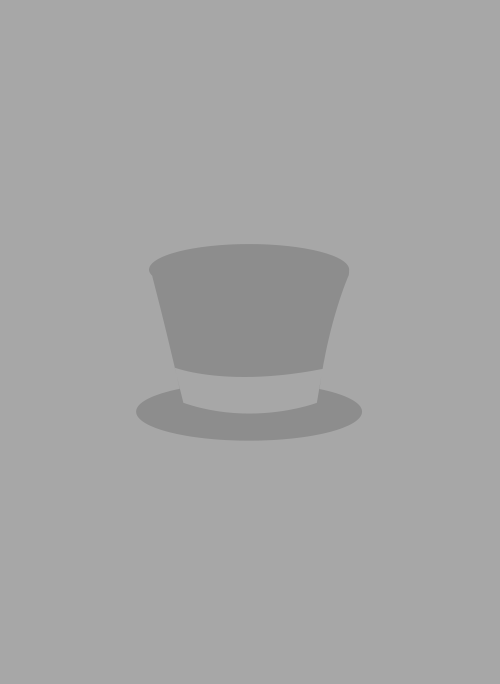「不味いじゃないか、今すぐ作り直しな! 全く、お前はどうして味噌汁もろくに作れないんだろうね。一郎は優しいから、お前みたいな女でも、可哀想だと思って嫁にしてあげたんだよ」
夏の昼下がり、郊外にある一軒家では、同居している姑にいびられ、無言で耐えている嫁の千香子がいた――。
千香子は、夫の一郎と三年間付き合い結婚したのだけれど、一郎は早くに父親を亡くし、母親のカツコに女で一つで育てられ、身内はカツコしかいない。そういう事情で、結婚後は同居することになった。
結婚前に会ったカツコの印象はとても良く、穏やかな物云いに、上手くやっていけると思っていた千香子は、自分の見る目のなさに心底後悔することになる。
結婚し、カツコと生活を共にして明らかになった本性。それは言葉では云い表せないほど酷かった。一郎がいる時には良い姑を演じ、千香子と二人きりになった途端、まるで鬼のように変化する。それがカツコの本性だったのだろう。それは表情だけではなく、口調や態度にも表れていた。
朝、一郎が出勤した途端、料理が不味かったと怒声を挙げ、千香子が掃除しているのを監視しながら文句を云い続ける。お昼ご飯を出せば、見ただけで不満を漏らし、食べながらも不満の言葉が止まることはない。そして、虫の居どころが悪いと、残した料理を千香子に投げつけることも多々ある。
千香子は頭にくるばかりだったけれど、愛する一郎のためにと我慢をし続けた。
夏の昼下がり、郊外にある一軒家では、同居している姑にいびられ、無言で耐えている嫁の千香子がいた――。
千香子は、夫の一郎と三年間付き合い結婚したのだけれど、一郎は早くに父親を亡くし、母親のカツコに女で一つで育てられ、身内はカツコしかいない。そういう事情で、結婚後は同居することになった。
結婚前に会ったカツコの印象はとても良く、穏やかな物云いに、上手くやっていけると思っていた千香子は、自分の見る目のなさに心底後悔することになる。
結婚し、カツコと生活を共にして明らかになった本性。それは言葉では云い表せないほど酷かった。一郎がいる時には良い姑を演じ、千香子と二人きりになった途端、まるで鬼のように変化する。それがカツコの本性だったのだろう。それは表情だけではなく、口調や態度にも表れていた。
朝、一郎が出勤した途端、料理が不味かったと怒声を挙げ、千香子が掃除しているのを監視しながら文句を云い続ける。お昼ご飯を出せば、見ただけで不満を漏らし、食べながらも不満の言葉が止まることはない。そして、虫の居どころが悪いと、残した料理を千香子に投げつけることも多々ある。
千香子は頭にくるばかりだったけれど、愛する一郎のためにと我慢をし続けた。